出版社内容情報
欧州において有機農産物はいまや「日常」的なものとなり、消費・流通・生産の現場は大きく様変わりし、「食」や「環境」への意識も変化した。本書ではドイツ、オーストリア、フランスの現場と、それを支える公共の役割を考察し、欧州での地殻変動の原動力を解明するとともに、日本における有機農業の将来像を提示する。
内容説明
欧州において有機農産物はいまや「日常」的なものとなり、生産・流通・消費の現場は大きく様変わりし、「食」や「環境」への意識も変化した。オーストリア、フランス、ドイツという最前線の現場と、それを支える公共の役割を考察し、欧州での地殻変動の原動力を解明するとともに、日本における有機農業の将来像を提示する。
目次
はじめに 欧州の有機の今と萌芽期にある日本
第1章 消費・流通の現場から―オーストリアのスーパーの事例
第2章 公的機関が果たす役割―欧州最大のマーケットとなったドイツ
第3章 生産の現場から―フランスの有機農家の挑戦
第4章 日本における有機農業の未来
補章 有機農産品による学校給食を実現するためには
著者等紹介
香坂玲[コウサカリョウ]
1975年生まれ。名古屋大学大学院環境学研究科教授。専門は資源管理・環境政策論
石井圭一[イシイケイイチ]
1965年生まれ。東北大学大学院農学研究科准教授。専門はEUの農業農村政策(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Porco
14
岩波ブックレットというシリーズだからなのか、もうちょっと知識のない読者に親切にしてほしかったかも。2022/07/03
遥
8
香坂玲さん、石井圭一さん著の「有機農業で変わる食と暮らし ヨーロッパの現場から」を読み終えました。この本では、有機農業のルーツや哲学の大切さ、ポーランドでの有機製品普及の要因、公共機関の役割、生産現場の課題、日本における有機農業の未来などについて述べられています。また、有機パンや学校給食における有機農産品の実現についても触れられています。2024/06/23
セヱマ
6
オーストリアの有機農業拡大はスーパーが牽引(ドイツも)、ドイツはハチを救え運動も一翼。少量多品目で家族経営で地産地消な有機農業こそが理想なのだというのは分かる。組織が企業化し有機が慣行化していくジレンマw、規模と効率性の追求の結果モノカルチャーの大量生産w。縮小していく地域に対し、地産地消だけで産業として成り立つのか?市民皆農業者なら素晴らしい。2024/02/19
kamekichi29
4
物足りない内容でした。。。2022/07/24
中村蓮
1
日本と比較すると、日本の農家もフランスの農家同様①ポリバレントで、②生産者ネットワークの協働によるイノベーション、③地元消費者とのつながりもあり、行政もドイツのように補助があり、公共調達も進んでいますが、大きく違うのはスーパーでの販売や消費者の意識的な購入など川下側だと思いました。 全体的な環境意識の低さというか。消費者は「中国産だ。何が入ってるか分からないなあ。」なんて言いつつも安いからってバクバク食べるし、生産者側も行政が視察に来てる前で当然のようにプラゴミやたばこの吸い殻を捨てるような。 2022/12/21
-
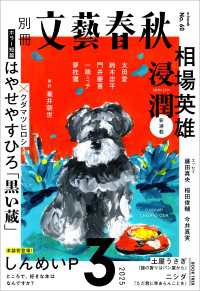
- 電子書籍
- 別冊文藝春秋 電子版60号 (2025…
-
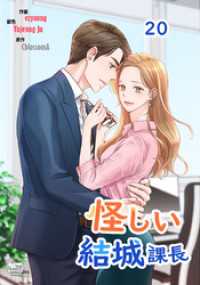
- 電子書籍
- 怪しい結城課長20 NETCOMICS
-

- 電子書籍
- 四人の夫 第44話 俺の嫁は彼女だけだ…
-

- 電子書籍
- カラダ、重ねて、重なって(5) 【電子…
-
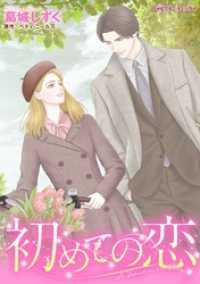
- 電子書籍
- 初めての恋【分冊】 12巻 ハーレクイ…




