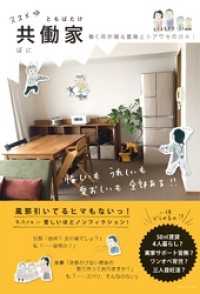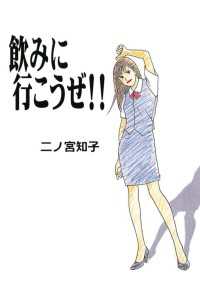出版社内容情報
若者を取り巻く社会環境は悪化する一方で,若年層における幸福感や生活満足度は高まっている.なぜか.
内容説明
近年、若者たちを取り巻く社会環境は悪化している。社会的格差の拡大とともに貧困も深刻化し、それらに起因するいじめや児童虐待も目立つようになっている。ところがその一方で、各種の意識調査によると若年層における幸福感や生活満足度は、逆に高まっている。この相反現象の秘密とはいったい何か?「宿命」をキーワードに、高齢層など他世代との比較、また時代による社会構造や意識の変化もふまえて解き明かす。
目次
第1章 相対的貧困率と生活満足度(拡大する社会的格差;社会的排除の進行 ほか)
第2章 高原社会に広がる時代精神(生活満足度の世代格差;増加する高齢者犯罪 ほか)
第3章 いにしえからの自分の本質(かけがえのない自分の誕生;地元というフロンティア ほか)
第4章 格差と幸福をつなぐ宿命論(生得的属性と期待水準;人間関係の比重の高まり ほか)
補論―「宿命」を問いなおす(分断線を越境する人びと;高原期における努力とは ほか)
著者等紹介
土井隆義[ドイタカヨシ]
1960年生まれ。筑波大学人文社会系教授。社会学。大阪大学大学院人間科学研究科博士課程中退。博士(人間科学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りょうみや
26
今の若者たちは親世代と比べ経済的に貧しくても幸福度が高いらしい。一昔前の家族や地域の煩わしい束縛はないし、自分と似た心地よい人たちとネットなどで出会えゆるく繋がっていられる。何より生活や金銭に対する期待値が最初から高くない。なので期待は裏切られないので幸福度は低くならない。努力すれば学歴を得て現状を変えられることは理解しつつも自分には難しいことが早い段階で気づいてしまっている。しかしそれが「宿命」と受け入れるのがよいのか。若者たちに自分は変えられることを知ってほしいと著者は訴えている。2023/07/15
いとう・しんご
10
読友さんきっかけ。直前に読んだ松井梓さんの本が丁寧な文献調査と全身全霊を賭けたフィールドワークによる力作だったのに、本作は既存の社会調査とマスコミのヒット作を並べて宿命的人生観に捕われる若年者達という空想社会学小説を作り出しているだけという印象でした。そもそも、そういう若年者を育てたのは著者達の世代であり、先行世代だったはずなのに、それを若者達に責任転嫁しているだけじゃぁないの!?と思ってしまったのでした。2025/05/16
ののまる
10
すごい現代の若者世代について勉強になった!2020/04/20
カラス
8
「宿命」というキーワードで現代の分断を読み解く本。右肩上がりの時代が終わり現代は成熟の時代、GDPがほぼ横ばいの「高原地帯」を歩んでいる。若者は自らを「宿命」で縛り、そして同時に安心する。諦めとは遠く、酸っぱい葡萄の論理さえない。別の世界など考えられず、今の境遇は努力できない自分のせいだから仕方がないと、努力主義を過剰に内面化してしまう。結果、生活は苦しいけれど、満足感は高いという奇妙なデータが産出される。土井隆義の本を読むのはこれで四冊目だが今回も当たりだった。2019/10/11
ichigomonogatari
8
すでに停滞期に入った日本で生まれ育った若者たちは、よりよき未来に期待するという意識すら生まれない。また人生への期待値が低いので、不満を持たず満足しているという。格差のある社会がそれぞれ閉じていて、各自自分の周りしか知らないのでたとえ劣悪でもそれが当たり前と感じるようになる。格差の壁は個人では乗り越えられないことを感じてはいるが、同時に自分の努力が足りないせい、と「努力主義」を思い込まされている。わかったようなわからないような。世代間で見える景色が全く違うことはわかった。2019/08/28