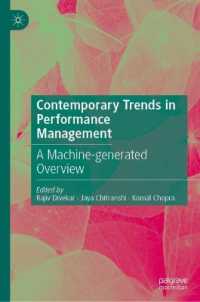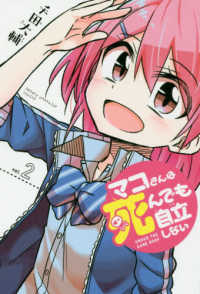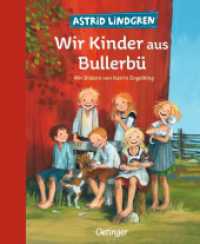内容説明
沖縄県宜野湾市にある佐喜眞美術館は、普天間基地に食い込むように建っている。この美術館は本書の著者が、米軍基地に接収されていた先祖代々の土地を取り戻して建てたもので、その最大のコレクションは丸木位里、丸木俊の「沖縄戦の図」である。美術館の歩みを通して戦後沖縄の一断面と、アートの持つ力が見えてくる。
目次
1 熊本の少年時代
2 学生運動から鍼灸師へ
3 軍用地代を使ったコレクション
4 丸木夫妻との出会い
5 「沖縄戦の図」を沖縄に
6 「もの想う空間」として
「沖縄戦の図」について―修学旅行生への説明
著者等紹介
佐喜眞道夫[サキマミチオ]
1946年、家族が疎開した熊本県甲佐町で出生。高校卒業まで熊本で過ごす。高校時代、真宗寺(熊本市健軍)の仏教青年会に参加。1974年、立正大学大学院文学研究科史学専攻を修了。1975年、絵のコレクションをはじめる。1979年、関東鍼灸専門学校を卒業。鍼灸院を開業(千葉・東京)。1994年11月23日、佐喜眞美術館を開館(沖縄・宜野湾市)。2011年、第33回琉球新報活動賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
26
庶民の生活を同じ目線で豊かに表現したのは、浮世絵だったのではないか(25頁上段)。 依里さんは地獄に行くと言い、戦争を食い止めることはできなかった。その罪において、と、ヒロシマを 見た画家として「原爆の図」を描き始めた(32頁下段)。平和な社会をつくるためには、市民一人ひとり の美的感覚の変革が基礎となるべきだ(上野省策先生、47頁下段)。 2015/05/06
tu-ta
1
丸木美術館で購入してすぐ読んだ。サブタイトルのとおり、佐喜眞美術館の軌跡がよくわかる。2014/07/19
Kei Takenami
0
佐喜眞美術館と『沖縄戦の図』の印象は忘れない。決して奢らず、真摯に72年前の記憶と沖縄と世界の未来に向き合う。そんな地道な作業の結晶だとおもった。奇跡のような物語だが奇跡ではない。同美術館に関わるひとと触れればわかる。2017/06/18
吉村花緒
0
戦時中も戦後も日本は沖縄を都合よく利用してきた罪深さを噛み締めた。戦時下に米軍に投降すると残虐に殺されるとされた内容は日本軍がアジアの国の人々にしてきたことと同じで、恐怖の裏返しであったことと、丸木夫妻の沖縄戦の図に目がない人々が多いのは戦争は人の心を壊してしまうからというのに戦慄した。アートを鑑賞することは作者や作品の対象と対話することであり、アートは人の内面を抉り出すので、実際の記録を読んだり見たりすることよりも説得力があり考えさせられる場合も多いのではないか。沖縄の人々に心安らげる日々が来てほしい。2021/08/25
ftoku
0
佐喜真美術館にて購入。「ありのままに感じろ」的な教えがつまらなく感じるタイプの人間なので、こういったアートコレクションの意図や経緯がわかる本はありがたい。2021/06/01