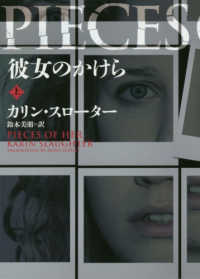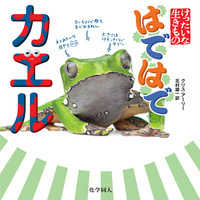出版社内容情報
1603(慶長8)年イエズス会宣教師らが日本布教のため心血を注いで編纂した辞書(長崎で刊行)の全訳.古代語から近世語への過渡期たる室町時代の日本語について,話し言葉を中心に,雅語・俗語・方言・婦人語等を含めて実に約3万2000語を採録し,語義・用例を示すほか,語法・発音にまで説き及び,近代辞書の内容体裁を備えている.キリシタン史料の白眉とされ,国語史研究に不可欠の文献.国語・ロマンス語学者の多年の協力により翻訳.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
秋色の服(旧カットマン)
2
一応、必要箇所だけ図書館で見てきました。イエズス会の本気度がよく分かる。結構、昔から今使っている日本語ってあるのね。人間はそれほど変わらず、技術だけが大きく変わっているのが歴史なのだろうか。斜め読みしてみると発見がある。こういう読書も面白いかも。2017/01/26
えんのしん
0
戦国時代の日本語を集めた辞書だがほぼ全部の語が現代語として通用する。言葉というのは変わってるようで変わらないのだなあとしみじみ思う。読み方の変わっている語もあって例えば国人は現代だとコクジンと読むが当時はクニュードと読んだらしい。狩人をカリュードと読むのと同じ系統だ。「武士Buxi」は軍人と説明されているが「侍Saburai」は貴族と説明されていて少々驚く。貴族なのか?すでに武家政権が始まって四百年が過ぎて、京都の公家は何の権力もない名ばかりの存在になってしまったのだなあと感じ入る。2025/02/27
-

- 和書
- HamaShoの本