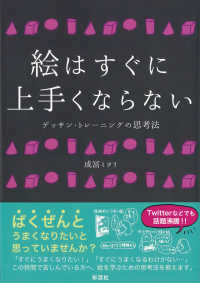出版社内容情報
親にすてられたのに明るく文才のあるヨーニー,母思いのマルチン,力のつよいマチアス,ちびのウリーなど,個性のちがう少年たちの織りなす,悲喜こもごもの群像をみごとに描きます.
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
69
1933年、ナチス政権の始まった年の作品だが、そんな影を感じさせない古き良き時代(の、おそらくはいい所だけ)を描く。高等中学と訳された、ギムナジウムの生徒のクリスマス前。楽しく、あるいは切ない思いが伝わる。イギリスならパブリックスクールがこんな感じかも。児童文学でもあり、学園小説でもあるような。最初は取っつきにくさを感じたが、半分ほど進んだ頃には、物語にすっかり引き込まれていた。今の日本なら逆に非難されそうな、先生の粋な計らいなど、心温まる話を新鮮な物語で読ませてもらった。2018/01/04
yamatoshiuruhashi
54
小学校5年生の冬休みに初めて読んだ(同じ高橋健二訳)。以来ケストナーファンとなり、幾度読んだことか。クリスマス前には本書と「クリスマスキャロル」を読み返すのが20代半ばまでの十余年の年中行事であった。改めて読み返すとケストナーの少年たちに送る温かくも鋭い指摘に大人になってからの自分を責められる。例えば「おこなわれたいっさいの不当なことにたいして、それをおかしたものに罪があるばかりでなく、それをとめなかったものにも罪があります」という一節。1933年の作品。この少年たちはその後の時代をどう生きたのだろうか。2022/01/10
NAO
52
クリスマス劇の練習、他校との抗争。クリスマス休暇を目前にしたドイツの学校風景が描かれ、その少し浮足立った雰囲気の中で、悩みを抱える少年たちの姿が浮かび上がってくる。ウーリーやマルチンの苦悩、「飛ぶ教室」という劇を作らずにはいられなかったさまよい人のヨーニーの孤独。好きなシーン、泣けるシーンは何カ所もあるが、マルチンが家に着いてすぐ「帰りの汽車賃もぼく持ってるよ」と言うところが一番好きだ。ケストナーの本を読んで本好きになった、私には大切な本。やっぱり、幼い頃から読み続けている高橋健二訳が一番しっくりくる。2015/12/25
ちえ
48
子供の頃から何度となく読んだ本。実はクリスマス本とは意識していなかったけれども、読友さん達のレビューで久しぶりに本棚からとりだした。この本は読むたびに胸かつまり涙を堪えるのが難しくなってしまう。一人一人の少年の悲しみ、涙、輝き。そしてどの先生も彼らに愛情を持って接していることが伝わってくる。ヨーニーやマルチンはもちろんだけど、子供の頃ウリーにとても共感していた。今も、自分に欠けていることに対してとても恥ずかしく感じるというところ、生きやすくはないけれど、その正直さに心うたれるんだ🎄2020/12/25
ちえ
46
クリスマスに向けて:子供の頃から何度も読んでいた飛ぶ教室。子供の頃は読み飛ばしていた、お話に入る前の章が大人になってからは心に響く。ー子供の涙の大きさについてー「この人生では、なんで悲しむかということは決して問題ではなく、どんなに悲しむかかということだけが問題です…私はただ、つらい時でも正直でなければならないと言うのです。骨のずいまで正直で」2021/12/21