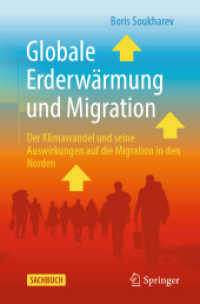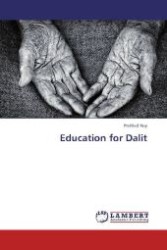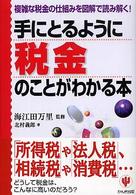出版社内容情報
18世紀ロンドンの裏通り.点灯夫,産婆,質屋,葬儀屋,薬屋,印刷屋など,さまざまな職業の見習いの少年少女が日々切実な思いで生きていた.かれらの喜怒哀楽を,物語性ゆたかに印象的に描く,ユーモラスな12編の短編連作.
内容説明
18世紀半ば。華やかな大都市ロンドン。だが、一歩裏通りに入れば、日々切実な思いで暮らしているさまざまな職業の見習いの若者たちがいた。夢と希望を紡ぎながら生きる少年少女たちの喜怒哀楽を、物語性ゆたかに、印象的に描く。中学以上。
著者等紹介
ガーフィールド,レオン[ガーフィールド,レオン][Garfield,Leon]
1921‐1996。イギリスの作家。美術を学ぶが戦争で中断し、従軍。戦後は生化学技術者として働く。1966年以後は、執筆に専念。歴史物を得意とし、とくに18世紀イギリスを舞台にした作品が多い。ギリシア神話を再話した『海底の神』(共著)でカーネギー賞を受賞
斉藤健一[サイトウケンイチ]
1948年福島県生まれ。東北大学大学院修了。元三重大学教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
NAO
76
18世紀半ばのロンドンは世界でも有数の大都会だったが、ディケンズの小説でも描かれているように、一歩裏通りに入れば、そこには貧しい人々がひしめき合って暮らしている。裏通りの子どもたちは、何らかの職業の見習い(徒弟)に出された。『見習い物語』は、夢と希望を紡ぎながらロンドンの裏通りで生きる、そういった少年少女たちを描いた連作短編物語だ。葬儀屋の見習いとライバルの葬儀屋のほのかな愛を描いた「バレンタイン」と、見栄っ張りな母子が本当の幸せを見つける「骨折り損」がよかった。2019/04/03
たつや
46
立派な歴史小説でした。日本の奉公と違い、ロンドンの見習いの制度は厳しい。制限が多い。少なくとも、親方が死んだら奥さんと結婚するというのは酷いと思った。2017/01/25
ぱせり
15
最初の物語から、物語の隅々まで小さな明るい光が飛び散っていったんだな、と上巻を読み終えた今、思っているところ。親方も見習いたちもほんとにいろいろ。起こる出来事も対処の仕方もいろいろ。でも、どれもちゃんと松明の灯りに照らされているよ。『バレンタイン』の「よくなってくる」話にくすくす。墓の下の死者たちも、びっくりして飛び起きそう。 2014/03/11
カラスノエンドウ
13
題名から想像したのは、厳しい修行に耐えながら健気に働く見習いの若者の姿。しかし、読み始めると「…?」「!?」途中からそれは確信に変わり、ニヤニヤ笑って楽しんだ。点灯夫・助産師・質屋・靴屋など様々な職人が18世紀半ばのロンドンの下町を彩る。 連作短編。死者に恋した葬儀屋の娘が登場する「バレンタイン」がとても良かった。滑稽でブラックな笑いもあるが、爽やかな後味。 印象深い鏡屋の娘には助演女優賞を。彼女は前衛的アーティストだと思う(笑)【祝・岩波少年文庫創刊70周年!】2020/04/12
ヴェルナーの日記
7
18世紀のロンドン下町における見習いたちの物語だ。本作の冒頭にも説明があるように、当時のロンドンの子供たちは、手に職をつけるため、ある年齢になると徒弟として親方の下で修業する制度(徒弟制度)があった。その期間が7年。日本で言えば、丁稚奉公に当たるが、7年間は年季奉公で、年季奉公が明けると、今度はお礼奉公といって2~3年は、親方も下に留まって安い賃金で働かなければならない。その後、上手くいけば暖簾別けできるが、実質0からのスタートなので成功を収めるのはかなり厳しい状況だった。2013/11/20