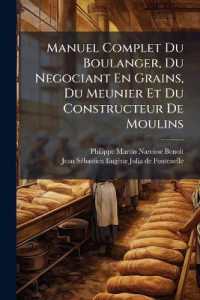出版社内容情報
原爆、そして被爆者のイメージは、どのようにつくりあげられてきたのか。「原爆映画」が誕生する敗戦直後から二〇〇〇年代に至る国内外の映像・文学作品を取り上げ、植民地主義、検閲、人種・民族とジェンダーなど、様々な視点から解き明かす。国境や学問領域を超え、広島・長崎を巡る日米の「知の生産」過程に迫った画期的研究。
内容説明
原爆、そして被爆者のイメージは、どのようにつくりあげられてきたのか。「原爆映画」が誕生する敗戦直後から二〇〇〇年代にいたるまでの国内外の映像・文学作品を取り上げ、植民地主義、検閲、人種・民族とジェンダー、トラウマなど、様々な視点から解き明かす。国境や学問領域を超え、ヒロシマ・ナガサキに関する日米の「知の生産」のプロセスに迫った画期的研究。
目次
序章 広島・長崎と表象の政治
第1章 ドキュメンタリーとしての『ヒロシマ・モナムール』―語られなかった「幻の映画」をめぐって
第2章 亀井文夫と一九五〇年代の初期原爆映画―被爆者をどう描くか
第3章 視られる者から視る者へ―「原爆一号」吉川清が問いかけたもの
第4章 日仏合作と核大国アメリカの影―『ヒロシマ・モナムール』における占領の記憶
第5章 林京子の被爆者「以上」の文学―一人きりのディアスポラ
著者等紹介
柴田優呼[シバタユウコ]
明治学院大学国際平和研究所研究員、アカデミック・ジャーナリスト。アメリカ、ニュージーランド、オーストラリア、日本の大学教員を歴任。コーネル大学Ph.D.(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ラッシー
-

- 電子書籍
- 異世界でスキルを解体したらチートな嫁が…