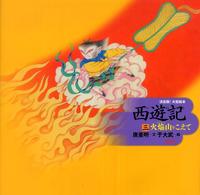出版社内容情報
全国の小学校数は、いまや明治時代よりも少ない。当たり前にあった学校は、急速に姿を変えながら、地域社会から消え去りつつある。だが、学校なしの教育は成り立つだろうか。新型コロナウイルスの感染拡大が与えた影響を読み解きながら、これからの学校、そして教育の条件を探る。学校事務の専門家による渾身の提言。
内容説明
明治期よりも少ない小学校の数、教育費の重い自己負担、授業のデジタル化による家庭への皺寄せ…。社会のインフラとしての学校を軽視する教育に未来はない。学校事務・財務の専門家が提言する、コロナ禍以降の学校のかたち。
目次
はじめに アフター・コロナの学校の条件
第1章 学校を防災の拠点に
第2章 教育情報化は「魔法の杖」か
第3章 消えゆく学校
第4章 変わる学校給食
第5章 完全無償の公教育を
おわりに 八つの提言
著者等紹介
中村文夫[ナカムラフミオ]
1951年、埼玉県生まれ。明星大学大学院修了。専修大学などを経て、教育行財政研究所主宰。専門は教育行財政学、学校事務論、教育施設環境論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
TAK.I
11
筆者は学校事務職員として38年間勤めた方。コロナ禍ということもあり、第1章が学校を防災の拠点にすることについて書かれ、珍しい。その後、教育の情報化や学校の歴史的経過と現状の課題を論じる。教育の無償化についての章では、自治体によって、教材や修学旅行、給食費などが補助されたり無償だったりする所もあることを知った。コロナ禍に乗じてデジタル教育に舵を切ったが、課題は山積。教育格差がさらに広がることが懸念される。学校教育を国や自治体、現場任せにするのではなく、地域で学校を育てていくことの重要性を説いている。2021/10/05
スパナ
0
元学校事務職員で、今は教育行政研究所の主宰を務める著者。 避難所としての学校、ICT教育、少子化と学校統廃合、学校給食、義務教育無償などのテーマで今後の学校のあり方を問う。昭和以前からの学校制度の歴史も踏まえて今の学校を考察していて、そこまで遡って話せる人はあまりいないのでは。とても参考になりました。2021/10/29