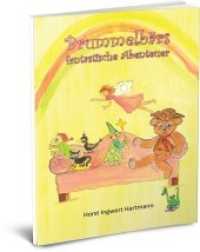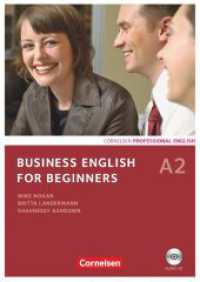- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
内容説明
コメはいつ主食になったのか。スシの起源はなにか。味噌・醤油はどのように普及したのか。だしの文化はいつ始まったのか。なぜ肉食は禁止され、いつ再開されたのか…。本書では、食文化研究の視点から、著者独自の巨視的な歴史区分を採用。日本の食の変遷と知られざる魅力を解き明かす、いままでにない食文化通史。
目次
第1部 日本の食文化史(稲作以前;稲作社会の成立;日本的食文化の形成期;変動の時代;伝統的な食文化の完成期;近代における変化)
第2部 日本人の食の文化(食卓で;台所で;外食、料理、飲みもの)
著者等紹介
石毛直道[イシゲナオミチ]
1937年千葉県生まれ。京都大学文学部卒業、農学博士。専門は文化人類学(食事文化、比較文化)。国立民族学博物館教授、館長をへて、同館名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。第24回南方熊楠賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ユウユウ
15
食卓につながる歴史2021/12/26
KEI
12
新聞の書評で興味を持ち図書館本。食から日本文化を読み解くという姿勢で書かれてあり面白く読めた。二部構成、一部は古代から現代に至るまでの食文化史、二部は日本人の食の文化について論じている。食に関わる語源も興味深い。時の権力者がその維持の為に、宗教や思想を用いて食文化をコントロールしていた。特に富国強兵の為の肉食や乳製品の推奨、太平洋戦に於ける日の丸弁当等は、この様な視点から見ると滑稽だ。日本人は海外の食を取り込んで独自の食文化を作り上げた。同様に世界に広る日本食がその風土に変化するのであろう。2016/02/16
ユウユウ
4
受け継いできた食がつくってきたもの2025/08/07
つみれ
2
日本の伝統!みたいに言われてることって大体明治くらいにはじまったやつで歴史浅いで〜とかあったりするけど、食文化もそんなんいっぱい。けど100年くらいやってたら、まあ伝統と言っても良いかと思えてきた、こんなにあると。有害でなければ。ナレズシ論が面白い。2025/07/16
takao
0
☆ちょっと内容詰め過ぎ。参考文献が基本、自著なのはいただけない。 2016/03/29