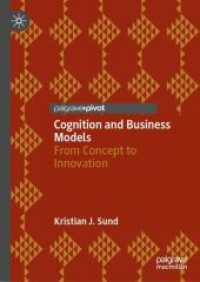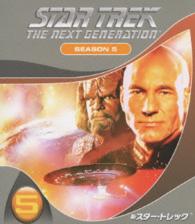出版社内容情報
30年代初頭、ベルリン。疾走する愛。拡大する恐怖。大使一家の手記に基づく戦慄のノンフィクション。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キムチ
44
手に取りやすい類から読んでしまったが思いのほか中身は柔らかく重い、昏い。1933年、ルーズベルトの「アメリカのリベラルのお手並みを見せてやれ」の一言で任地に赴くところから始まる。駐独大使トッド・・実は本職歴史学者。彼はもとよりアメリカ、いやいや連合国はヒンデンブルグ後のナチ政権を甘く見ていたのがヒシと感じられる。一極集中の権力掌握に奔走するヒトラーの本性が見えてくるとトッドが懊悩するさまが感じられる。ラーソンがまとめ上げたこの力作・・日記や資料・証言を基にしたというが恐るべきエネルギーとただ感嘆するのみ!2017/08/17
Shintaro
39
ヒトラーの台頭から長いナイフの夜事件で独裁を掌握するまでドイツに駐在した、アメリカ大使ドッドと、その奔放な娘マーサの視点から見る第三帝国の変容。大使一家に残された膨大な書簡をノンフィクションとして掘り起こした。ドッド大使は、着任時はナチにも人間性が残っていると考え、影響力を行使してよい方向へ導こうとした。しかしユダヤ人への迫害が明らかになり、ドッドは希望を失い、ナチスへの警戒を促す。マーサはナチス高官や外交官などとの交流を深める。第三者の客観的な視点で、第三帝国ウォッチャーにとっては重要な文献であろう。2015/11/07
星落秋風五丈原
30
外交官は外国語に端麗で交渉が巧く上流階級の人達との洗練された会話を楽しみ…カッコいい。それまで駐独アメリカ大使として赴任した人達は確かにそんな人々だった。しかしドッドは「国のために外国に嘘をつくことができるような機知もないし、二枚舌を使えるタイプでもない」。にもかかわらずアメリカは彼を代表として選んだ。アメリカの関心事は、その頃密かに話題になっていたユダヤ人問題でもドイツ国内の動きでもなく貸した金の速やかな償還。今の難民問題と同様にユダヤ人問題は「自分の国に来られたら困る」という本音がどの国にもあった。2015/11/17
春ドーナツ
19
不可視のままで続くことはない。けれども可視化は終わりの始まりを意味する。そして未来は誰にもわからない。だから自分に都合の良いことをぼんやり、意識の少し下の辺りで当てにしている。本書を読み終えた後そんなことを考えていた。自分自身の日々の過ごし方でもある。ううむ。エリック・ラーソン氏の翻訳された本を読み続けて今回が一応の区切りとなった(四冊目)。毎回切り口が斬新で今回も「駐独アメリカ大使の視点」というのは大変興味深かった。そこから見えてくる世界のいろいろな相貌。頭の中で「たられば」することを繰り返してしまう。2018/10/10
funuu
18
先進国の人々はドット大使のような環境にいる。近くにヒトラーがいても「素晴らしい指導者に見えたり」「世界を破戒させかねい人物に見えたり」当時のような悲惨な出来事がインターネット、テレビあらゆる種類の媒体で見ようと思えば見える。私も含めて大部分の人はチラッと見たり感心がなかったりするうちに、また「ハイル」と言っているかも。田中さん舛添氏を引きずりを降ろすのを喝采したように。私も「ハイル」と会社では言っている一人ではある。それも終わりに近い。2016/06/16
-

- 電子書籍
- 悪女が恋に落ちた時【タテヨミ】第89話…
-
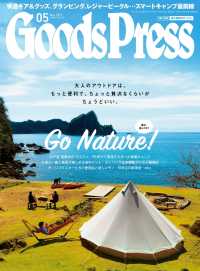
- 電子書籍
- GoodsPress2019年5月号