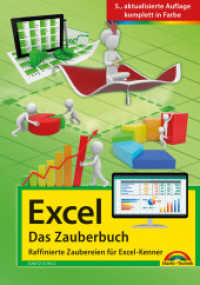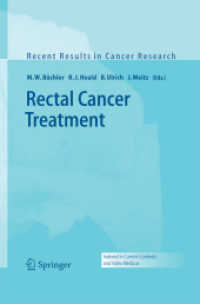内容説明
雇用の空洞化や民主主義の機能不全がとどまるところを知らない現代日本において、公教育は未来の社会に向けて何をしていけばよいのか。本書は、教育の中の能力観の問題、職業を手に入れるための教育という考え方、そして、市民形成の役割をめぐり、教育を改革する方向を多面的に論じる。『教育には何ができないか』から十年余。理論と実証、歴史と現在を往還しながら展開される、著者渾身の問題提起。
目次
教育は何をなすべきか―公教育の役割を再考する
第1部 能力・職業・市民(社会変動と「教育における自由」;能力にもとづく選抜のあいまいさと恣意性―メリトクラシーは到来していない;生まれつきの能力差に応じた教育?―教育の早期分化論の問題点;職業教育主義を超えて―学校の役割を再考する;子どもたちに市民になってもらうための教育―政治的教養の冷凍解除について;「ボランティアを通して学ぶ」ことの両義性と微妙さ)
第2部 歴史と現在との往還(大正時代の新教育と社会―澤柳政太郎と成城学園の位置;教育における絶えざる失敗と意図せざる成功―戦前期中等工業教育をめぐる教育政策について;戦後の青少年政策とこれからの子ども・若者)
ポスト震災の教育をどう考えるか―本書のまとめに代えて
著者等紹介
広田照幸[ヒロタテルユキ]
1959年生まれ。日本大学文理学部教授。教育社会学。東京大学大学院教育学研究科博士課程修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。