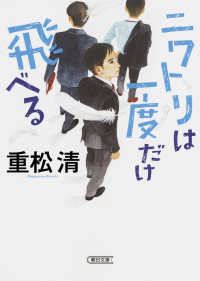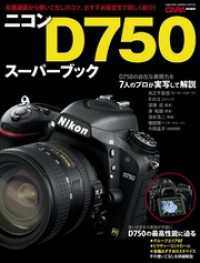内容説明
「何の役に立つのか」と問われるたびに、文学は、いつでもささやかな弁明をくりかえしてきた。時間と空間を超えた「共通の感覚」をもたらし、個と普遍とを結びつける文学こそ、この危機の時代において真に希求される営みではないだろうか。長年にわたって日本とフランスを往還しつつ思索を深めてきた碩学が贈る希望に満ちた文学論。
目次
第1篇 文学のために―現代フランスに見られる「文学」再考の動き(理論の見地から;教育と研究の現場;創作家の立場)
第2篇 重層をなす「読み」の楽しみ―フランスで読む日本文学(アンドレ・ジッドと永井荷風―文学上の「影響」の内実;ウイリアム・ブレイクと大江健三郎の「美しい月」―創作の源泉としての読書;重層をなす「読み」の楽しみ―バルト・小林秀雄・本居宣長・紫式部を通じて「作者」を追う;葛西善蔵における「わたくし」と「おおやけ」―「現実」を読む「私小説」作家;小林秀雄と自然科学―自然を読む科学者と詩人;グローバリゼーションに対する森有正の観点―個に徹する読みから表現の普遍性へ)
第3篇 文学は言語の壁を超えられるか―共通の基盤のために(フランス語のl’oeuvreと日本語の「作品」のあいだで;フランス語に「拷問される?」日本文学;フランス語圏における『源氏物語』の受容―「日本のプルースト」から「フランスの紫式部」へ;フランス語圏における日本近代文学研究の現状―「読む歓び」と「原点礼賛」;知と血と言葉と―「母語」をめぐる小林秀雄と森有正の選択)
著者等紹介
二宮正之[ニノミヤマサユキ]
1938年東京生まれ。少年期より音楽と文学を好む。1965年東京大学大学院仏語仏文学研究科博士課程中退、パリ留学。以来、在欧。1965‐68年エコル・ノルマル・シュペリユールに在籍。ロジェ・ファイヨルの指導を受ける。この時期から森有正と親しく交わる。1969年フランス国立東洋言語文化大学INALCOの教職に就く。同大学助教授、パリ第三大学比較文学科講師を経て、1992‐2003年ジュネーヴ大学文学部日本学科教授。現在、ジュネーヴ大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ドミニク