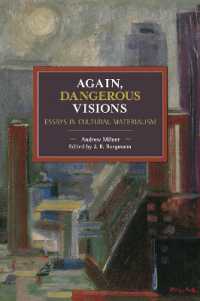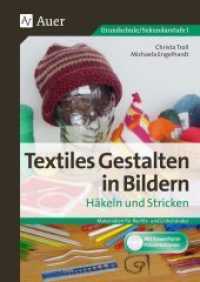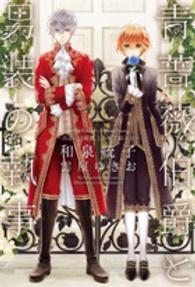内容説明
東西の知的エリートたちが互いに交流し平和裏に議論を重ねた輝かしい“文明の対話”の時代に西欧学術が東アジアにもたらしたものとは?
目次
第1部(明末天主教と死生観―中西対話の底に流るるもの;数学即理学―『幾何原本』とクラビウスの数理的認識論の東伝について)
第2部(清代前半の満洲語書籍にみる西欧の科学と宗教;西洋楽典の東漸―『律呂正義』続編について;戴震と西洋暦算学;清朝中期の学と暦算の学)
第3部(科学精神と「理」の変容―中華民国初期における清代学術評価論争;在華イエズス会士による中国史叙述;『毛詩品物図考』より見た18世紀における新しい「知」の形成)
著者等紹介
川原秀城[カワハラヒデキ]
1950年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。東京大学大学院人文社会系研究科教授。中国朝鮮思想史・東アジア科学史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。