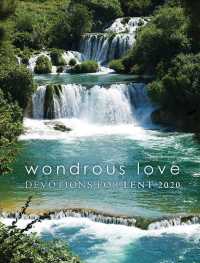出版社内容情報
数量の大まかな把握はヒトだけでなく多くの動物にもできるが、ヒトだけが正確に数え上げ計算する能力をもつ。その能力に必要なのが数の言葉だ。数学的思考の起源は言語にあるのだろうか。心理学・認知神経科学に加え、近年めざましく発展した機械学習技術による成果も用いて「我々ヒトにとって数学とは何か」を問う。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mim42
14
数学の認知科学の一般向け解説書。基本的な考え方は「数学は、言語能力により拡張されたパターン認識である」。私が深掘りしたいと感じたのが、領域間プライミングにより数式文法構造が言語の文法構造に影響を与えている可能性示唆だったり、線分連結・回転操作における操作圧縮→複雑性認知と下前頭回活動の関係等。下前頭回は文章理解と計算に共通した文法処理の領域らしい。教育による数量と数字の変化を説明する、記号分離仮説も興味深い。発達による数字位置⇄位置数字課題における対数性の消失、概算の分布における中心の対数性も。2025/06/11
nagata
7
数学的思考とその奥にある根幹的な能力みたいな話かな?と思いきや、数学的思考の根源をもっともっと認知科学のレベルにまで掘り下げて追及する代物。でもそれだけ気づきは多い。数量の大まかな把握はヒト固有の能力ではなく動物レベルでのパターン認識。しかし、言語を駆使するヒトは、より深遠な構造を紡ぎだす。と思いきや、岡先生の「数学的思考は計算や論理とは別物」とぶった切る人もいる。確かに情緒を持ち出されると手強いけど、それだけ数学は一筋縄ではいかないのだろう。だから面白い。2025/09/30
maghrib
5
特に5章以降が面白かった。数式の再帰構造と自然言語文法の木構造が類似しており、同じ脳領域で処理している可能性、数学は自然言語文法を利用して発展した可能性、AI言語モデルの注意機構は数式処理でも同じ対応があること等。従って数学が人間の身体や文化に依存していて普遍性がない可能性や、さらに、思弁的に発展した数学がなぜ物理現象を説明できるかの理由である可能性が語られる(さすがにこれは著者も懐疑的)。先日のNHKEテレのインタビューで数学者山下真由子も数学の人間依存性を語っており、興味深かった。2025/05/15
gokuri
3
数学の脳機能についての研究を語る入門書といった風合いながらも、一般人向けで読みやすい。 ドットパターンを利用しながらfMRI(機能的磁気共鳴画像法)により、脳活動の位置を特定したり、類似パターンを判別してしまうという技術に驚く。 その結果、数の数え方、計算時の脳の活性化と、文書、単語構成を理解する脳の活性化の比較により、脳の動きの類似性がわかるという。 一方では、人間は文字認識なくしては、4つくらいまでしか物の個数を瞬時に判断や記憶もできないというから、改めて数字、文字、数式等の発明に驚かされる。2025/12/28
ゆうやけPC
0
プログラミングに続き数学も言語野を使うことを知ることが出来た。言語野はもしかして筋道を立てて考える部分なのだろうか?2025/11/04