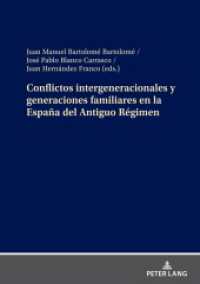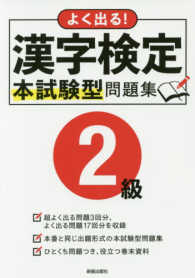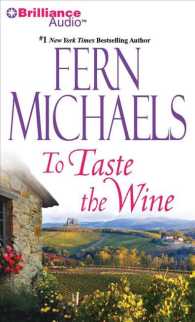出版社内容情報
チンパンジーやボノボ、他の霊長類、哺乳類との比較から見えてきた、言語や芸術の本質、暴力の起源、愛とは。
内容説明
すべての生命は進化を通してつながっている。人の心の何が特別で、どんな道すじで今あるような人の心が生まれたのかを知るために、人間にもっとも近いチンパンジー、ボノボに始まり、ゴリラ、オランウータン、霊長類、哺乳類…と比較の輪を広げていこう。そこから見えてきた言語や芸術の本質、暴力の起源、そして愛とは。
目次
心の進化を探る
アイ・プロジェクト
アフリカに行く
ボッソウの森で
親と子と仲間と
子どもを育てる
相手の心を理解する
仲間とかかわる知性
文化を生み、引き継ぐ
言語の起源
芸術の誕生
暴力はどこからきたか
希望を生み出す知性
著者等紹介
松沢哲郎[マツザワテツロウ]
京都大学高等研究院特別教授・霊長類学者。1950年愛媛県松山市生まれ。1974年、京都大学文学部哲学科卒業、理学博士。1977年11月から「アイ・プロジェクト」と呼ばれるチンパンジーの心の研究を始め、野生チンパンジーの生態調査もおこなう。2016年3月に京都大学霊長類研究所を退職し、同年4月、京都大学高等研究院特別教授に就任。霊長類研究所兼任教授、中部大学創発学術院特別招聘教授、京都造形芸術大学文明哲学研究所所長、中部学院大学客員教授、公益財団法人日本モンキーセンター所長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
那由田 忠
15
チンパンジーなどヒト属ヒト科に近い霊長類の認識能力を、長期間研究してきた松沢さんの研究、比較認知科学と呼ぶものの歩みをまとめた本。タイトルにあるように、他人と協力する心がどこまであるのかを、ヒトとチンパンジーの新生児の行動の違いから読み解いていく。ニホンザルは新生児が母ザルにしがみついた中で歩き回る。チンパンジーは母ザルが片手を少し新生児を抱いて移動する。人間は床に新生児が置かれて母と子が見つめ合い、子は手を自由に動かす。ここに手を使う力や心の交流、言葉の発達の原点を見ていく。2018/09/03
月をみるもの
12
チンパンジー「アイ」の共同研究者として名高い、ホモサピの研究者松沢哲郎。てっきり犬山で実験中心の研究をしてきたのかと思えばさにあらず、ギニア・ボッソウで野生のチンバンジーを追いかけ、京大文学部哲学科の山岳部員としてヒマラヤの山も登る。チンパンジーの道具使用が文化として伝搬していくさまは、ホモサピの遺跡に残されている石器がどのように使われ発展していったのかを彷彿とさせる。アフリカから出て地球の隅々まで行き渡った一霊長類の行く末を見極めようとする彼の次の目標は、なんと「月」である。2019/08/10
アラム
8
長年霊長類の研究に取組んでいる松沢教授が著者の本です。「比較認知科学」を通じ、人間と動物の心を探ります。人類が野生を失い、運動能力において動物より劣ることは周知の事実ですが、人間は、記憶力においてチンパンジーより劣るという事実は、なかなか驚きです。では人間は何が優れているのか?想像力です。人間は自分が見ている世界の外側に意識を向けることができるのです。想像し、共感する心の進化が人間に進歩をもたらしたのでしょう。2020/06/25
takao
2
人間の特徴は利他性。人間には、草原のチンパンジーと森のボノボの特徴がキメラとなっているのではないか。 2020/03/20
rymuka
1
読書録あり → http://rymuka.blog136.fc2.com/blog-entry-84.html 、 http://rymuka.blog136.fc2.com/blog-entry-96.html2021/11/06