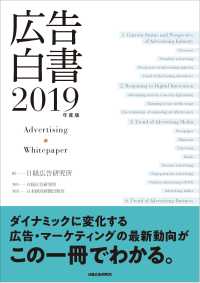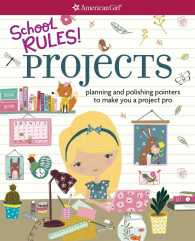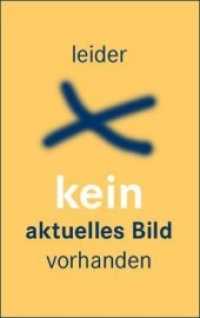内容説明
モラル、いわゆる道徳とか倫理というと、人間に固有の客観的な理性に基づく判断だと考えられ、主観的で情動的な判断と区別される。しかし、最近の脳科学や進化心理学の研究によれば、モラルは、人類が進化的に獲得したものであり、むしろ生得的な認知能力に由来するという。脳自身が望ましいと思う社会は何かを明らかにした本。
目次
1 善悪という主観の脳科学
2 五つの倫理基準
3 政治の脳科学
4 信頼と共感の脳科学
5 評判を気にする脳
6 幸福の脳科学
著者等紹介
金井良太[カナイリョウタ]
1977年東京都生まれ。京都大学生物物理学科を卒業後、オランダ・ユトレヒト大学で実験心理学PhD取得。カリフォルニア工科大学にて、下條信輔教授のもとで視覚経験と時間感覚の研究に従事。現在は英国サセックス大学・サックラー意識研究センターにて准教授(Reader)。主な研究テーマは認知神経科学からのアプローチによる意識研究と、脳科学の現実世界への応用技術の開発(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





にんげんの旅本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
スパイク
18
おもしろい!心とか感情とかは論理で語り得ぬもの。「倫理」「道徳」といった感性に関わる問題はこれまで、社会的な文脈(例えば哲学)で語られてきた。それを科学で解き明かそうとしてる。まだまだ(というか、ほとんど)解ってないのだが善し悪しの判断を脳のどの部分で行っているのかは科学的には解っているという。だから、たとえば保守的な考え方を持つかどうか、なんてのも脳を調べれば、ある程度わかってしまう。ゆえに遺伝もする(もちろん環境の影響のほうが大きいけれど)。「幸せ」なんて概念も科学的解析を行っていてとても興味深い。2014/07/20
ほじゅどー
16
脳は無意識のうちに自分の行動を決めている。オキシトシンは愛や絆を強め他人を信頼し、ストレスや不安を軽減するホルモン。ハグで増える。幸福は収入とは無関係。幸福度は日本以外ではU字型カーブ(若い時は幸福、30代後半〜50代に低下、その後上昇)だが、日本人だけは若い時からどんどん下がり続け老後の再上昇がない。「困った時に相談できる友人がいるか?」「信頼できる集団に属しているか?」これらが幸せの要因。多様な友達と交流の機会を増やすことで、社会性の脳機能を発達させることが出来る。2014/01/25
樋口佳之
14
政治的信条の遺伝的傾向の部分はにわかに納得できない部分もあります(3歳は既に大きく社会的影響を受けているのでは?)が、全体的には遺伝子決定論ではなく社会的影響特に成長期の影響がその後の倫理的傾向に現れると言う話でした。/「負の互恵性」/政治的にリベラルな人間では大きかった場所である。これもまた、平等や公平性を社会に求めるリベラルな思想と、他者を思いやる共感力が共通の脳の基盤をもっている/素人目にもまだまだ研究途上の分野だと思いました。著者が強調している人間の幸福向上につながっていけばいいですね2016/10/19
Mc6ρ助
13
今だけ金だけ自分だけな政権から六割が「こんな人たち」に放り出された日本、果たして人間に良心があるのか気に掛かって手に取った本。功利主義的な現代経済学では捉えきれない、倫理観や共感、信頼性などが人類の進化の過程で器質的に獲得されたという少し論点が違うかも知れないものだった。救いが無いわけではないけれど、今開き直っている人達につける薬があるわけではなかった。2022/10/01
月をみるもの
11
文字通りの意味での「幸福の科学」2019/09/18