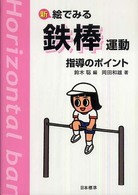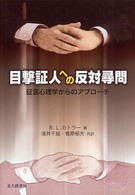内容説明
書誌学とは時代の産物としての本そのものから「情報」を得るための技術である。宝暦年間に出版された板本を手にした時、いかにすれば宝暦という時代の手ざわりを実感できるのか。近世文学研究の泰斗が、長年の経験の蓄積をもとに、江戸の板本を手にとり理解するための基礎知識を平易に伝授する。和本リテラシーを育む最良の入門書。
目次
第1章 板本というものの性質
第2章 板式
第3章 書型
第4章 装訂
第5章 分類
第6章 板本の構成要素―書肆の受け持つ部分
第7章 板本の版面
第8章 本文の構成要素―著述内容に関わる部分
第9章 刊・印・修―板(版)・刷り(摺り)・補(訂)
付論 板株・求板
著者等紹介
中野三敏[ナカノミツトシ]
1935年生まれ。九州大学名誉教授。近世文学専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
17
本の大きさも様々で、7類型写真で示される (図1、61頁)。 豆本というのは岩波文庫みたいなのだろうか? 本屋が書物出版すると権利が生じる。 これを、板株(はんかぶ)と称した(288頁)。 著作権の原点を考えるには必要な権利。 電子書籍の時代に、 改めて本の構造とは何ぞや、 と思って借りるとそれなりに、 得られるものがあるかもしれない。 2014/04/20
山がち
0
江戸の和本に関する装丁が非常に丁寧に書かれていてとても面白かった。和本の大きさや種類だけではなく、その綴じ方、紙の種類、紙の折り方などかなり広い項目にわたって、本当に丁寧に書かれている。どういった装丁の本が、どういった本として出版されることが多いのかというように、装丁と本の関係がきちんと結びついている。江戸の和本について少し本を読む前に、まず読んでおきたいように思った。また、江戸時代の出版についても触れられていた。その中の重版・類版などに関する項目は特に興味深かった。覆刻の際の装丁の変化などもまた面白い。2013/07/02
笠井康平
0
大学で教わった知識が多くて、つまり基本をしっかりまとめてある良い本なのだと思った2013/08/01
Yamanaka Shinya
0
江戸の板本の基本的なことがわかる。わかりやすくて、面白い。2013/01/27
-
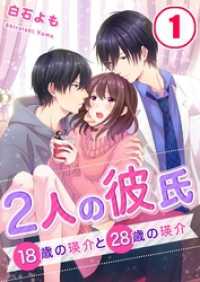
- 電子書籍
- 【フルカラー】2人の彼氏~18歳の瑛介…