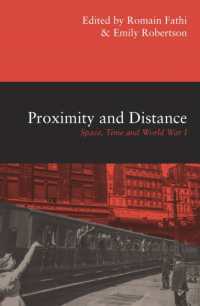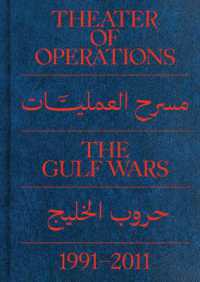内容説明
情報化、グローバル化が加速するメディア社会。公議輿論の足場として、歴史的教養の重要性はますます高まっている。しかし、こうした現実の課題に対して、「大きな物語」が失われたあと、これまでの歴史学は充分に応えてきただろうか。公共性の歴史学という視点から、理性的な討議を可能にする枠組みとして二一世紀歴史学を展望する。
目次
1 歴史学ゼミナールの誕生―歴史学はどのように生れたのか(教訓的歴史から歴史研究へ;大学の歴史学 ほか)
2 接眼レンズを替えて見る―歴史学を学ぶ意味とは何か(社会史が輝いていた頃;世界システムとメディア史 ほか)
3 歴史学の公共性―歴史学は社会の役に立つのか(趣味の歴史と大衆の趣味;国民大衆雑誌の公共性 ほか)
4 メディア史が抱え込む未来―歴史学の未来はどうなるのか(メディア史の発展段階論;進歩史観と情報様式 ほか)
5 歴史学を学ぶために何を読むべきか(「読む歴史」のために;「書く歴史」のために)
著者等紹介
佐藤卓己[サトウタクミ]
1960年生。京都大学博士(文学)。現在、京都大学大学院教育学研究科准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かんがく
11
著者の本は数冊読んだことがあるため、具体的な歴史研究の内容については既知のものが多かったが、大学などにおける実体験が豊富に書かれており、歴史研究に向かう姿勢として刺激を受けた。メディアというテーマが歴史学において果たす役割の大きさを改めて感じた。2021/03/22
politics
6
本書はメディア史分野を開拓した著者による歴史学入門書。著者の学部時代からいかに歴史学やメディア史を学んでいったかの来歴が語られており、自伝としても読める。ハーバーマスへの違和感、8.15神話への警告など興味深い話題も多く、佐藤メディア史学への入門としてもおすすめである。2021/06/25
柳田
6
☆5。おりにふれて見返す。2018/08/27
かろりめいと
4
メディア史の専門家による「歴史とは、歴史学とは何か?」。著者の本はこれで4冊目なので、歴史研究者としての関心の移り変わり・来歴がわかり、とても面白かった。p38~「あなたは大衆ですか?」と、p116~「「世論(せろん)の輿論(よろん)化」の未来へ」が赤裸々で印象的。2021/02/28
ぽん教授(非実在系)
3
メディア史からみた歴史学の入門書、というなかなかにユニークなコンセプト。従来型の歴史学やってる人にも、ライトに歴史を趣味として楽しんでいる人にも、社会科学や情報学の立場からメディアに取り組む人(自分はここに位置する)にも参考になる一冊。岩波が著者のような戦後民主主義にも一定の批判を加える人に本を書かせたのか・・・という面でも注目できる。2013/01/12