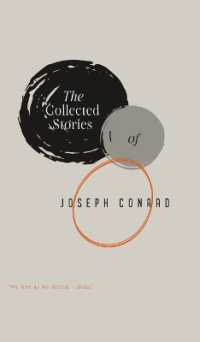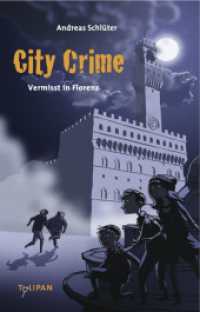内容説明
過去はどのようにして知りうるのか。有限な人間は神であるかのように唯一の正しい歴史を語ることはできません。私たちは過去を想い起したり、その痕跡などから歴史に迫ろうとします。そのとき「歴史的事実」とされるものは何なのか。「客観的事実とは何か」について探究する科学哲学・分析哲学の知見いっぱいの刺激的な講義。
目次
第1日 歴史哲学と科学哲学
第2日 歴史認識をめぐる論争
第3日 出来事としての歴史/記述としての歴史
第4日 歴史における説明と理解
第5日 歴史の物語り論(ナラトロジー)
第6日 過去の実在
第7日 歴史記述の「論理」と「倫理」
補講 過去の実在・再考
著者等紹介
野家啓一[ノエケイイチ]
1949年生まれ。東北大学文学研究科教授。専攻、現代哲学・科学哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たこらった
5
科学哲学者らしい比喩横溢。直接知覚できない「過去の実在」は飛跡からしか確認できない素粒子の「実在」と同じ構造を持つ、と。「歴史history」の原義は「探究」で、物理学のような理論的「探究」の手続き(巨大実験装置や量子力学等の理論的ネットワーク)が歴史学にも求められる(史料批判や年代測定)。理論的存在は「間主観的」な構成物であり「社会的制度」でもある。だから訂正修正がある。燃素の実在が否定されたように神武天皇の実在も否定されている。過去は将来の新たな経験に開かれた「探りを入れると存在してくる」実在なのだ。2024/01/23
柳田
4
岩波現代文庫で読む。歴史学科学なのかという問いは、人文(科)学は科学なのか、という問いに通じるのだが、さまざま、特にドイツで、歴史学を科学として成立させようという試みが行われてきた。野家さんが提唱する「歴史の物語論」には、実証史学の方面からは批判が寄せられているようだが、はたしてこういう議論は、歴史学者の研究の方法とかには直接影響を与えるものではなさそう。あくまでも、科学哲学、歴史哲学内部の研究だと考えてよいのだろうか。もっとも、これは講義録でわかりやすく書かれているので、『物語の哲学』とかみないと。2018/02/18
void
4
【★★★☆☆】「物自体」のような強い実在論(形而上学的実在論)を排し、「過去の実在」は「実定性」と「間主観性」が欠かせない社会的公認物であるとする、穏当な議論。タイムマシンがない以上流れる時間の中で生きているし(過去は知覚できず想起するのみ)、公共物としてフィクション以上の実在的強度があるよ(内在的実在論)、と。 本としては掴みの梗概が難しすぎるが、日を追うごとに(講義を文章に起こしたもの)内容はつかみやすくなる。が、どの水準・どの枠内の話なのかが混乱しやすいのは、いくつかある質問・批判にも表れている。2013/05/30
あに太
2
過去の実在・客観性について考察する本。過去が人間の存在を超えて実在するとし、神の視点から過去を捉えようとする素朴実在論に対して、言語によって過去を構成する「過去物語り論」を対置する。過去はそれ自体として存在するのではないが、フィクションのように捏造して良いものでもない。「過去はわれわらの想起や物証から独立にどこかに「存在」するものではなく、社会的に公認された公共的手続きを通じて「生成」していくもの」なのである。素朴な実証主義でもなく、歴史修正主義でもない第3の道を本書は示していて、示唆に富む。2024/12/03
kyakunon22
2
テンポが良く、現象学や古典的な哲学を科学哲学や分析哲学、或いは日本哲学の文脈と組みあわせながら、しかも歴史という具体的な対象に則して語るのが非常に小気味よい。2020/02/21