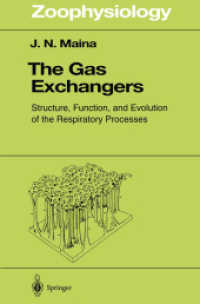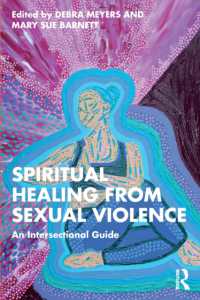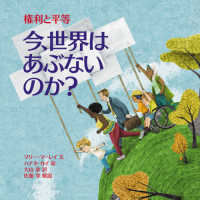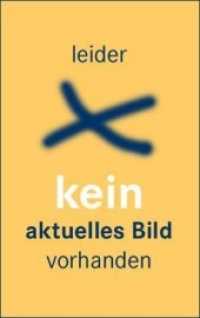出版社内容情報
ペリー来航から終戦までの百年間、教育、産業、テクノロジーなどの分野を含めて、「音楽」をめぐるあらゆる営みが、劇的な変容を遂げていった。第一巻では、軍楽隊の導入とその民間への広がりによって誕生した市中音楽隊、ジンタ、チンドン屋などの様相を描き、併せて学校唱歌から軍歌、壮士演歌までの展開を叙述する。
内容説明
音楽の「近代」を空前の規模で俯瞰する著者渾身のライフワーク。第一巻では、軍楽隊の導入とその民間への広がり、学校唱歌から壮士演歌までの流れが詳細に叙述される。
目次
トントントンで始まる歴史
第1部 軍楽隊の市民化―練兵場から公園へ(軍楽隊;鹿鳴館;日比谷公園奏楽)
第2部 民間楽隊の系譜―ブラスバンドの土着化(市中音楽隊;少年音楽隊;ジンタ;チンドン屋)
第3部 学校唱歌の通俗化―教室から大道へ(唱歌;軍歌;「鉄道唱歌」;寮歌;演歌)
著者等紹介
細川周平[ホソカワシュウヘイ]
1955年生まれ。東京芸術大学大学院音楽研究科博士課程修了。現在、国際日本文化研究センター名誉教授。専門分野は近代日本音楽史、日系ブラジル文化史。著書に、『遠きにありてつくるもの―日系ブラジル人の思い・ことば・芸能』(みすず書房、2008年、読売文学賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。