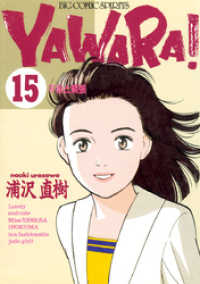内容説明
マルクスの遺産を抜きに現在もないし未来も存在しない。そう言い切ってデリダは、共産主義の崩壊とともに歴史は終わったとするフランシス・フクヤマの主張を痛烈に批判した。デリダがマルクスの精神を呼び起こそうとしたのはなぜなのか?本書は、『マルクスの亡霊たち』に即しながら、デリダが生みだした脱構築という思考方法の理解に読者をみちびく。
著者等紹介
シム,ステュアート[シム,ステュアート][Sim,Stuart]
イギリス、サンダーランド大学教授。批評理論・文化理論
小泉朝子[コイズミアサコ]
1969年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。早稲田大学大学非常勤講師。イギリス文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
つゞみ@223tudumi
1
デリダ強化期間、入門書その3。歴史を終焉させようとする思想に対する、デリダの「ことはそんな単純じゃない」という主張がまとめられている。学べたのは「不可能性だからこその正義」と「亡霊」について。贈与など典型的なものだけど、もし正義が成り立つなら、その正義は不可能なところにある。そして正義が成り立たない為に、ベターな答えを出そうとする僕らと、亡霊がこの世にいるんだよ、みたいな。2012/06/28
芙美夫
0
この本は、一頃に流行った「歴史の終わり」をめぐる議論に対する、デリダの反論を説明しながら、デリダの基本概念である「脱構築」や、彼の著書『マルクスの亡霊たち』を解説している。主意としては、「〔フランシス・〕フクヤマの主張〔注:「歴史の終わり」に関するもの〕はイデオロギーを悪用した詐欺と大差ないものだと証明し」ながら、冷戦後こそマルクスについて議論すべき(或いはそうせざるを得ない)という主張がなされている。デリダ理解にもよい本だが、それ以上に「歴史の終わり」をめぐる議論について、簡潔に知ることができた。2016/02/05
平井良樹
0
マルクス主義、修正主義、マル経などマルクスを巡る名称はたくさんあるが、共産主義と共に滅んだのはマルクスの思想全てではない。経済学の話は分からないが、思想家として、20世紀の歴史の中に確かに刻印された彼の思想は看過するにはもったいない。 難解なデリダの思想を少しだが紐解いてくれる良書。2014/01/09
ShiTan
0
言葉は不確実なものでありその意味は先送りにされる(差延)のであって、ある解釈を与えたとしてもそれは恣意的なものでしかない。それと同様に、歴史のなかのとある出来事の意味も先送りにされる。ソ連の崩壊は歴史の終焉を意味しないし、共産主義の消滅とリベラル民主主義の勝利を意味しない。その意味は先送りにされるため、共産主義は消滅などせず、なお「亡霊」としてこのリベラル民主主義につきまとうことになるのだ。フクヤマの言う歴史の終焉論はリベラル民主主義における強者の自己保身のための恣意的な解釈に過ぎない。2012/11/08
gerumanium
0
フランシス・フクヤマから提出された「歴史の終わり」に関する議論をデリダの「マルクスの亡霊」という応答と対比し、デリダの立場や思想を理解しようとした本。フクヤマ=アメリカ人、デリダ=ヨーロッパ人として捉え、対比することでその現代の思想的流れがより明確になると思われる。2010/10/14