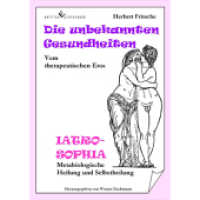出版社内容情報
現代科学と哲学に残された最大の謎「意識」。リベットの実験を始め近年のさまざまな科学的知見によって、意識に関する従来の考え方は大きな変更を迫られている。脳科学・認知科学の最新成果を踏まえ、意識をめぐる基礎的・哲学的問題を平易に解説する。
内容説明
リベットの実験をはじめ、近年めざましく発達した脳科学・認知科学の成果を踏まえて、古代から哲学者や思想家を悩ましてきた「意識」や「自我」に関する基礎的・哲学的問題をわかりやすく解説する。
目次
1 なぜ意識は謎なのか
2 人間の脳
3 時間と空間
4 壮大な錯覚
5 自我
6 意識的な意志
7 変性意識状態
8 意識の進化
著者等紹介
ブラックモア,スーザン[ブラックモア,スーザン][Blackmore,Susan]
1951年生。心理学者、サイエンスライター
筒井晴香[ツツイハルカ]
東京大学大学院総合文化研究科博士課程在籍・日本学術振興会特別研究員(DC1)
西堤優[ニシツツミユウ]
東京大学大学院総合文化研究科博士課程在籍
信原幸弘[ノブハラユキヒロ]
1954年生。心の哲学。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
51
脳科学や心理学の研究動向をコンパクトにまとめた本だが、驚くべき結論の入門書だ。最新科学は人間の身体だけでなく脳や心の機能に次々にメスを入れているが、究極の課題についての論争が尽きない。デカルト以来の哲学的課題ともいえる意識とは何かという課題だ。著者は様々な説を紹介しながら一つの仮説にたどりつく。人間の意識も、自我も、自由意思も壮大な錯覚に過ぎない。脳の働きがあるだけで、それを意識する「意識」が錯覚ならば、「意識とは何かという問いかけ」自体がないので、すべて解決する、と。身も蓋もないとはこのことである。2014/10/27
袖崎いたる
9
実際のところ、意識という代物はその幻想的実在性を踏まえておかなければならないのだろうね。デカルトへと退行する勇気は科学の発展から生産的に思えないとする見解も重々しい。本書は意識がハード・プロブレムと目されて穿たれた中心の周縁を巡る諸理論の解説となっている。ときたまその中心を覗こうとすると、あわや二元論の罠に陥りそうになるドジっ子の図…という形で先行研究から距離を取ってみせたり。その意味でデネットの「物語的重力の中心」という言葉は、まさに意識のその中心を志向しようとする思考の末路のことと言っていいのかもね。2017/03/27
みのり
4
フロイトの話が出てくるかと思いきや、かなり科学的な話、宗教から見た意識、動物の意識など、いろんな方面から意識について切り込んでいき、結論は意識などはあるように見えて実はないのかもしれない、少なくとも私たちが思っている形とは全く違うものではないかという結論だった。わたし自身は、動物の意識は、言語や人間との関わりが関係する気がしている。爬虫類には意識があるように見えるものとそうでないものがいるように見える。2024/02/17
サラダ
3
「意識とは何か」を、哲学、脳神経科学、心理学、仏教などの成果を紹介しながら、痛み、錯覚、夢、催眠術、薬物、瞑想などを考えていくことで、意識の正体を探していきます。「意識は錯覚だ」という同じような結論が書かれた前野隆司さんの「脳はなぜ心を作ったのか」を先に読んでいたので理解の大きな助けになりました。好感の持てる翻訳でした。2018/06/06
Mabo
3
意識とは錯覚であるという結論はなかなか許容しがたい。 デネットが否定した『デカルト劇場』がこれまでの意識についての基本認識だったけど、結局全ての説が推論の粋を出ないんだよなあ。他の説によった本も読んでみたい。2014/10/05