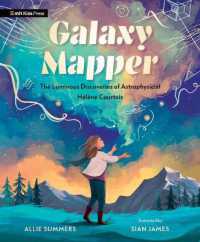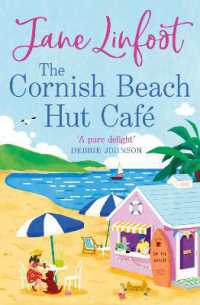出版社内容情報
幕末から明治期,「翻訳」という営みを通じて,日本語の文体はどのような自己認識をもち,変化していったのか.それは単なる外来概念の移入ではなく,書き言葉と話し言葉に隔たりがあり,漢語・雅語・俗語の絡み合う日本語が,自らを組み換えていく経験であった.その諸相を,当時のテクストや言説に即して浮き彫りにする.
内容説明
幕末から明治期、「翻訳」という営みを通じて、日本語の文体はどのような自己認識をもち、変化していったのか。それは単なる外来概念の移入ではなく、書き言葉と話し言葉に隔たりがあり、漢語・雅語・俗語の絡み合う日本語が、自らを組み換えていく経験であった。その諸相を、英語学習教科書、聖書、横浜言葉、日本語文法書など、豊富な事例から浮き彫りにする。
目次
想像のアメリカ言葉
ヨコハマ雑種語
異国ことば
ことばと世界
命がけ/命取りの英語
異国の人別にて終らんも本意ならす
ハジマリニカシコイモノゴザル
First Teacher of English in Japan
やわらげ、訳す
音の領略〔ほか〕
著者等紹介
亀井秀雄[カメイヒデオ]
1937年生まれ。群馬県出身。北海道大学名誉教授。市立小樽文学館館長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
16
翻訳は、自国の言語システムにおける兌換券的な価値と、他国の言語との 交換価値という二重性に直面して、その調整をはかる行為(ⅹⅳ頁)。文化経済学の中に言語資本概念を導入していく研究も重要だと思う。文明を発展段階的に序列化する意識は、明治に入って、地球は丸いという観念と共に一般化、未知な領域はいずれ知によって埋められるはずという観念が生まれる(23頁)。ペリーと仙八(34頁)。仙八は水兵に好かれていた。グリフィス『明治日本体験記』にも登場する。 2014/09/21
bapaksejahtera
8
本書は岩波の新日本古典文学大系明治編の月報連載を補遺して纏めた物。明治以降、日本語の文体確立の変遷を、英語翻訳の歴史を通じて探った、よく纏まり格調高く知見に溢れた著作となっている。古く日本には漢文脈の導入に当り、漢語には対応する倭語を当てると共に当て嵌らぬ語は概念そのまま移入するという、直訳の文化があった。英語にもこの方式が活用された為、漢文体の訳が広まる。これに対し江戸期の読本や戯作、更には古典文学のヒラ言葉文が一種の低徊や韜晦の気分で翻訳に生ずる。これが今日の文体に変容した様だ。この本は手元に置きたい2021/03/01