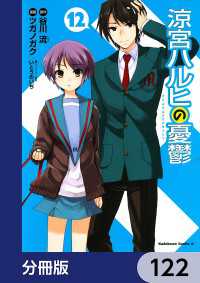出版社内容情報
私たちの日々は,何気なく過ぎていく.著者はその一瞬一瞬に古今東西あらゆる文学作品を感じ,言葉を紡ぎ,やさしく語りかける.精緻な文学研究に裏打ちされた筆致によって,日常生活が連想術のように文学作品とつながり,私たちが生きる一コマ一コマを彩る.のびやかな感性と知性が,体中に満ちてゆく文集.
目次
芝
時間を食べる
鹿に抱かれて
冬眠状態
満ち欠けのあいだに
からっぽの熊
待つことのかたち
詩と唐辛子
ハノイの朝は
城は城でも〔ほか〕
著者等紹介
蜂飼耳[ハチカイミミ]
1974年神奈川県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了。詩集に『いまにもうるおっていく陣地』(紫陽社、第5回中原中也賞受賞)、『食うものは食われる夜』(思潮社、第56回芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞)など。絵本に『うきわねこ』(絵/牧野千穂、ブロンズ新社、第59回産経児童出版文化賞ニッポン放送賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件