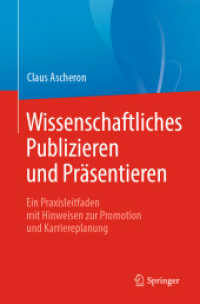内容説明
西洋の衝撃とともに成立した日本近代。その軋みの中で不敬事件を通過した内村鑑三は、無教会なるキリスト教を唱えはじめる。教会・組織・制度をもたず、雑誌・書籍等の「紙上の教会」を媒介とする無教会キリスト教―それが天皇制、大正教養主義、戦争とナショナリズム、戦後啓蒙、社会科学の導入といった日本近代の重要課題との関係で果たしたユニークな役割を、思想史とメディア史の交点から立体的に論じる。
目次
序章 無教会キリスト教とは何か(教会への問い、近代への問い;無教会の社会性をめぐって―先行研究の検討;歴史社会学という方法)
第1章 無教会の出現(信仰と愛国―内村鑑三と不敬事件;紙上の教会―無教会運動の初期構想;「無教会」の存在論―読者たちの宗教運動)
第2章 無教会の戦争(教養と宗教―大正教養主義と無教会運動の継承;民族の救済―矢内原忠雄の学問・信仰・政治;「無教会」の境界線―キリスト教ナショナリズムの臨界)
第3章 無教会の戦後(啓蒙の精神―南原繁、矢内原忠雄の宗教的啓蒙;正統と異端―キリスト教ブームと無教会運動の拡大;「無教会」のゆくえ―戦後社会科学の宗教運動)
終章 「紙上の教会」の日本近代(読者宗教という視座;教養宗教・文芸的公共圏・ナショナリズム;無教会と宗教の近代)
著者等紹介
赤江達也[アカエタツヤ]
1973年、岡山県生まれ。台湾国立高雄第一科技大学助理教授。博士(社会学)。筑波大学第一学群人文学類卒業。同大学院博士課程社会科学研究科修了。日本学術振興会特別研究員(慶應義塾大学)を経て、2008年より現職。専攻は歴史社会学、宗教社会学、メディア史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
fishdeleuze
みを
季京 洸和
trazom