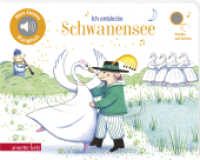出版社内容情報
「柿喰へば鐘が鳴るなり」と詠まれ,「早く芽を出せ柿の種」と急かされ,季語にも年中頻出する柿.次郎柿,富有柿,干し柿,柿ピーと,文学でも食卓でも馴染み深い柿は,日本の原風景に典型の木であるとともに,いまやKAKIとして海外にも流通している.甘柿とは限らない,ときには渋柿に難渋し,体当たりネンテン先生,柿を極める一冊です.
内容説明
子規のかじった柿はどんな柿?「柿喰へば鐘が鳴るなり」と詠まれ、「早く芽を出せ柿の種」と急かされ、季語にも年中頻出する柿。次郎柿、富有柿、干し柿、柿ピーと、文学でも食卓でも馴染み深い柿は、日本の原風景に典型の木であるとともに、いまやKAKIとして海外にも流通している。柿尽くしのエッセイ集。
目次
1 (カキノミの花;早く芽を出せ;庭先の柿 ほか)
2 (帶のところが渋かりき;双柿舎の先生;帶は司令塔 ほか)
3 (ひりひりごわごわ;柿の団子とシャーベット;柿の木問答 ほか)
旅ののち(空飛ぶ柿;柿をもぎつつ柿を食べ;柿の木の上より ほか)
著者等紹介
坪内稔典[ツボウチネンテン]
1944年愛媛県生まれ。本名=としのり。俳人、佛教大学文学部教授、京都教育大学名誉教授、俳句グループ「船団の会」代表。2010年『モーロク俳句ますます盛ん』で桑原武夫学芸賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
17
甘柿は富有と次郎。 前者は1902年公表。 岐阜県瑞穂市居倉(いくら)が 原産地(35頁)。 存じ上げなかった。 漱石のあだ名は柿(47頁~)。 正岡子規が名付け親。 渋柿。博士号辞退の執拗さ。 また、美濃加茂市の干し柿で、 堂上蜂屋柿(どうじょうやちやがき) があり、桐の箱入り、値段も高い(56頁)。 渋が抜けるとは、タンニンという成分が 凝固し、水に溶けなくなること。 2014/05/26
田中寛一
12
サラッと読んでしまおうかなと開いたものの、柿にまつわる俳句や料理、食べ方さらには結婚と繋がっていた柿、初めて知ることも多く、メモを取っていたらじっくり読むことになった。小説の中にはこんな風に描かれている、俳句にはこう取り上げられている、と。とくに結婚と柿との関わりを興味深く読んだ。柿、干し柿、熟柿が食べたくなった。2013/09/19
けいちゃん
1
秋の日差しに柿の木がなんとも似合うこと!そんな日に一読。2020/10/25
まきんぼ
1
柿って日本人と結びつきが深い食べ物なのね〜(*^^*)とニヤニヤ。柿好きなので、嬉しい本でした。早くこいこい、柿の季節!2013/05/10
笛吹岬
1
みじかな樹木である柿の木をめぐる民俗とその文学的表現である俳句。2012/11/04
-

- 和書
- セザンヌ