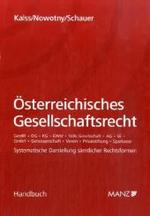出版社内容情報
上方落語四天王――松鶴・米朝・文枝・春団治の芸の魅力とは? 著者はその答を求め,実際の演目を例に挙げながら,具体的に論じていく.演者の声・口調・間・仕草など細部にまでこだわる手法により,知られざる芸の本質が鮮やかに浮かび上がる.随所に,著者の芸を見詰める温かな視線と鋭い洞察が光る,画期的な四天王論.
内容説明
六代目笑福亭松鶴、桂米朝、五代目桂文枝、三代目桂春団治。彼らは、戦後間もない頃、相前後して上方落語界に入門した。時には助け合い、また時には競い合って芸を磨き、やがて一世を風靡、四天王と称されるまでになる。滅亡寸前だった上方落語を復興させた功績は大きい。それぞれに異なる個性・芸風で人々の心をとらえた四天王。その芸の魅力とは何か?著者は、実際の演目を例に挙げながら綿密な考察を加え、芸の本質を鮮やかに浮かび上がらせる。演者の声・口調・間・仕草など細部にまでこだわった分析は、落語口演を聴き続けてきた著者ならではのものである。四天王への敬愛の念と、その芸への鋭い洞察が光る、画期的な四天王論。
目次
第1章 米朝落語の考察(『地獄八景亡者戯』;『たちぎれ線香』 ほか)
第2章 松鶴の話術―繊細と稚気(声の魅力―“音”の可笑しさ;やはり『らくだ』、酒のネタから ほか)
第3章 文枝の落語―五代目松鶴からの進化(丁稚は、喜六に通じる;ハメモノ落語を描いても ほか)
第4章 春団治の世界―舞踊と落語の融合(『代書屋』;『いかけ屋』 ほか)
第5章 大阪の古今亭志ん朝
著者等紹介
戸田学[トダマナブ]
1963年大阪・堺市生まれ。作家。2004年上方お笑い大賞秋田實賞受賞。大阪藝能懇話会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
oldman獺祭魚翁
fseigojp
百鉄
かもい
ぐうぐう
-
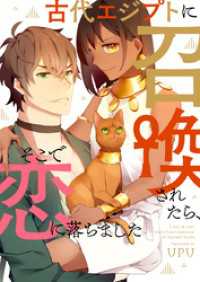
- 電子書籍
- 古代エジプトに召喚されたら、そこで恋に…