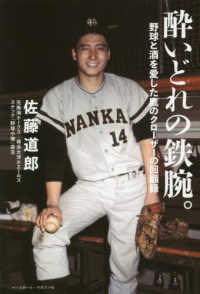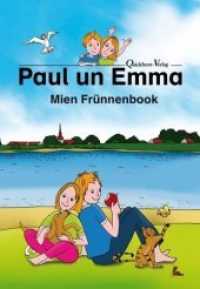出版社内容情報
前世紀の終わり、作家は自らの足で世界の紛争地帯を旅した。戦禍に苛まれた、ふつうの人々に接して感じた悲しみ、酷薄さ、寂しさ、無力感を想起し直し、いま一度、平和の意味を、成熟した小説家としての目をとおして問い直す。
内容説明
前世紀の終わり、作家はみずからの足で世界の紛争地帯を旅した。黄熱病に罹患しかねない地の果てで目にしたものは、なんだったのか。戦禍に苛まれた、ふつうの人々に接して感じた悲しみ、酷薄さ、寂しさ、やるせなさ、無力感を想起し直し、いま一度、平和の意味を、成熟した小説家としての目をとおして問い直す。
目次
黄色い紙の事情
イズント・シー・ラヴリィ
雨の女たち
戦車の墓場
紅い花
人を待つ人
ひまわり
プノンペンで転んだ
螢が
メラーキャンプ
彼の戦場
花火
著者等紹介
原田宗典[ハラダムネノリ]
1959年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。1984年に「おまえと暮らせない」ですばる文学賞佳作(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件