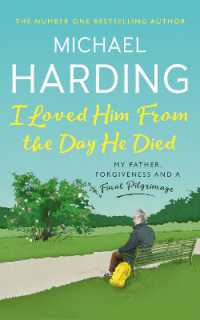出版社内容情報
対話し,考えるとはどういうことか.「子どもの哲学」「哲学カフェ」の実践をふまえた原理的考察.
内容説明
教育ではアクティブ・ラーニングの推進が叫ばれ、産業ではAI化とそれへの対応が議論される。そんななか、創造的な思考力や対話力のよりいっそうの育成強化が重視されている。しかし、そもそも思考と対話はどんな関係にあるのか。「考える」と「思う」はどう違うのか。対話する身体は、どのように考えているのか。誰もが安心して自分の考えを表現する場を確保し、維持できること、つまり対話における安全性(セイフティ)の条件とは何か。―「子どもの哲学」「哲学カフェ」の豊富な実践をふまえて探究する。
目次
序章 岐路の時代の対話と思考
第1章 ソクラテスは問答で何がしたかったのか
第2章 思考とは何か(1)―情念と問い
第3章 思考とは何か(2)―対話との関係
第4章 私の中で誰が話し、誰が思うのか―哲学対話とオープンダイアローグ
第5章 対話する身体はどのように考えているか
第6章 合理性と非合理性、そして架け橋としての感情
第7章 対話・教育・倫理
著者等紹介
河野哲也[コウノテツヤ]
1963年生まれ。立教大学文学部教育学科教授。慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程修了。博士(哲学)。専門は哲学、倫理学、教育哲学。NPO法人「こども哲学・おとな哲学 アーダコーダ」副代表理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サアベドラ
26
思考とは何か、対話とは何か、そして思考における対話の役割とは、などといったテーマを著者が携わっている「子どもの哲学」や「哲学カフェ」での経験や先達の哲学者の論考を基に論じた一般向け哲学書。2019年刊。小中学生を対象に哲学的テーマを一緒に考える「子どもの哲学」と、不特定の大人が集まって一定のルールのもとで哲学的議論をする「哲学カフェ」。なんとなく聞いたことがあったこれらをちゃんと知れたのが収穫。本書で議論されている内容については、哲学的文章に慣れていないこともあって正直そこまで頭に入ってこなかった。2020/01/06
koji
19
本書を私なりに要約すると、「AIの進展による人間疎外」やら「普通でない人を排除する風潮」等今・未来への不安が大きくなる中で、私たち大人はそれに立ち向かう若者にどんな武器を与えられるかを問い、それは対話・思考を経て得られた哲学であり、そのために教育における「子どもの哲学」の必修化を提唱するものです。では、対話・思考の意味・効果は何か。本書に幾つかキーワード(身体活動性、驚き、なぜ・何か・どのように、新しさの発現、リズム、コンセンサス合理性、普通の怖さ、真理の探求等)があげられています。深く考えさせられました2020/02/28
かんがく
15
アクティブラーニングに思考力と、近年教育界で注目されている「思考」と「対話」の問題について、長年「子供の哲学」に携わっている著者が語る。専門化により分断が進む現代社会を対話により全体化するという試み。民主主義と平和の実現のためには教育現場における哲学的対話が不可欠である。twitterなどでの相手を叩くための政治談議などを見ていると、開かれた対話の重要性がよくわかる。対話の目的は新しさ。散歩とユーモアが重視されていて、街歩きとお笑いが趣味の自分は無意識に対話的・思考的に生きているのかもと思った。2020/05/21
唯誠
8
私たちは日常的に会話をしている、対話ではなく会話。対話とは真理を求めるものであり、何かの問いに答えようとしたり、自身の考えが正しいのかを知ろうとし、真理を探究する会話のことであり、情報を検索すれば得ることができる単純な事実ではなく、検討しなければ得られないものを探る時が、対話というもの。 普通であったり、空気を読むの空気に従っている限り、その社会に「なぜ?」という存在はなく、対話も存在しない。個人の生活を楽しめればいいという思考で、公共の問題に無関心では、日々考えずの会話を重ねているに過ぎないと説く。2021/02/11
izw
7
対話は単なる会話ではなく、真理を求める会話、何かの心理を得ようとして互いに意見や思考を検討し合うことだという。「哲学カフェ」や小学校での「子ともの哲学」の実践経験を元に、哲学的対話ともいう対話の大切さを説いている。普通は、一人で対話的に思考する、読書しながら著者との疑似的に対話することも「対話」と捉える場合もあると思うが、それは対話ではないと断言し、他の人と対話することでのみ、真理に近づくことができることを強調している。まあ、そうなのかもしれない。2020/02/26
-

- 電子書籍
- 世界で動きだす国民運動 プランデミック…
-
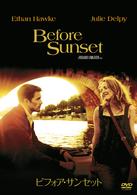
- DVD
- ビフォア・サンセット