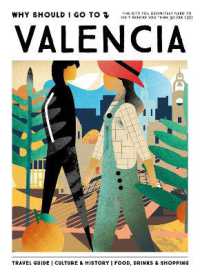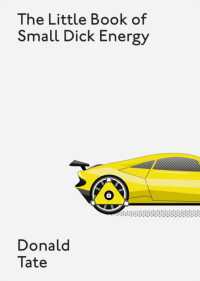内容説明
作家は、さまざまな場所を訪ね歩いた。ダウン症の子どもたちのアトリエ。身体障害者だけの劇団。愛の対象となる人形を作る工房。なるべく電気を使わない生活のために発明をする人。クラスも試験も宿題もない学校。すっかりさま変わりした故郷。死にゆく子どもたちのためのホスピス…。足を運び、話を聞き、作家は考える。「弱さ」とは何か。生きるという営みの中に何が起きているのか。文学と社会、ことばと行動の関わりを深く考え続けてきた著者による、はじめてのルポルタージュ。
目次
いいんだよ、そのままで―ダウン症の子どもたちのための絵画教室
たいへんなからだ―身体障害者の劇団「態変」
愛のごとく―「人間以上」のものを愛することについて
電気の哲学者―非電化工房代表の藤村靖之博士
山の中に子どもたちのための学校があった―南アルプス子どもの村小学校
尾道―「東京物語」二〇一三
ベアトリスのこと―子どもホスピス、マーチン・ハウス前編
ここは悲しみの場所ではない―子どもホスピス、マーチン・ハウス後編
著者等紹介
高橋源一郎[タカハシゲンイチロウ]
1951年生まれ。作家。明治学院大学国際学部教授。1981年、『さようなら、ギャングたち』(講談社)で第4回群像新人長編小説賞優秀作受賞。『優雅で感傷的な日本野球』(河出書房新社、1988年)で第1回三島由紀夫賞受賞、『日本文学盛衰史』(講談社、2002年)で第13回伊藤整文学賞受賞、『さよならクリストファー・ロビン』(新潮社、2012年)で第48回谷崎潤一郎賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヨクト
ruki5894
saga
Foufou
Naomi
-

- 電子書籍
- 家族の幸福度を上げる7つのピース