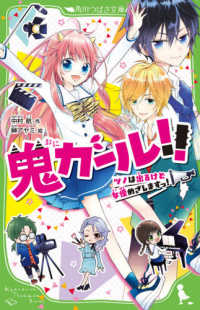出版社内容情報
国立競技場の外壁は全国の杉の板で覆われた。今、私たちの目の前にあるのは小さな点や線である――。建築家は風通しのよい物のあり方を求め続けて、木や石、そして土などさまざまな物質との会話を繰り返し、ついに新しい世界の扉を開いた。未来を考えるすべての人のための方法序説。待望の書き下ろし。図版200点収載。
内容説明
トビケラの幼虫は、小さな点のような身近な素材を集めて巣を作る。この虫をまねて、身体のような建築を作れないだろうか。あるいは、日本の伝統木造建築が磨いてきた、細く、移動する線を、今再び取り戻すことはできないだろうか。一枚の布が、テント暮らしを続けるベドウィン達の生命を守っていたように、面の持つしなやかな力を活かせないだろうか。建築家は、自然や歴史、そして量子力学のうちに点・線・面の新しいあり方を探り当てる。木、石、土など、物質と対話を繰り返しながらたどり着いた新たな世界、その扉を開くまで。
目次
方法序説(二〇世紀はヴォリュームの時代;日本建築の線とミースの線 ほか)
点(大きな世界と小さな石ころ;ギリシャからローマへの転換 ほか)
線(コルビュジエのヴォリューム、ミースの線;丹下健三のずれた線 ほか)
面(リートフェルト対クレルク;ミース対リートフェルト ほか)
著者等紹介
隈研吾[クマケンゴ]
1954(昭和29)年、神奈川県生まれ。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了。コロンビア大学建築・都市計画学科客員研究員をつとめた後、90年、隈研吾建築都市設計事務所を設立する。慶應義塾大学大学院、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校にて教鞭をとった後、09年より東京大学大学院教授。初期の主な作品に、水/ガラス(1995年、全米建築家協会ベネディクタス賞受賞)、那珂川町馬頭広重美術館(2000年、村野藤吾賞受賞)などがあるほか、近年注目を集める作品として、V&A・ダンディ(2018年)、国立競技場(2019年)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- DVD
- はじめの一歩 VOL.19