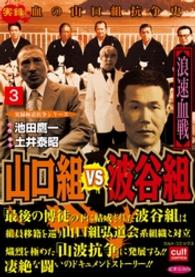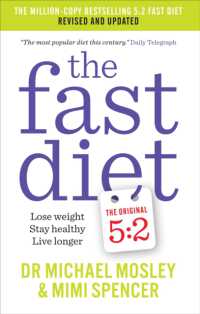内容説明
「私たちは歩きたい。そのためには摩擦が必要だ。ざらざらした地面に戻ろう!」―自らの哲学を、日常言語の働きの理解に向かって大きく転換させたヴィトゲンシュタインの主著『哲学探究』が、清新な訳文によって格段に近づきやすいものとなった。遺稿にさかのぼって新たなテクスト整備がほどこされた新校訂のエディションにもとづく待望の新訳。
著者等紹介
丘沢静也[オカザワシズヤ]
1947年生まれ。ドイツ文学者。東京大学大学院修士課程修了。首都大学東京名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
踊る猫
32
流石にニーチェの翻訳家が手掛けただけあって良く言えば詩的であり(ニーチェの哲学をウィトゲンシュタインは「詩」と評価していたのではなかったか?)、悪く言えば情緒的。もっとゴツゴツした即物的な訳で読みたいと思ったが、この読みやすく情緒に訴え掛ける訳でもウィトゲンシュタインの凄味は見えて来る。流れを成しているようで、実は思いつき(失礼!)が突発的にアチコチに散らばっているという印象もある。その思いつきに触発されてこちらも思いつきを重ね、そこから粘り強く考えていくも一興、人に話して苦笑されるも一興。使える本では?2020/01/05
吉野ヶ里
23
「はい。哲学おしまい。」って本。言語の意味はその使用にある。言語ゲームの切れ味は抜群だけれども、ウィトゲンシュタインはまだ私的なものや、絶対的基準の存在を探してるんじゃないかなって思った。本当は誰よりも彼が私的なものを探しているし、価値基準を探してるんじゃないかな。読んでからしばらく経つの内容の要約はもうできないけど。使われてる比喩がとにかく秀逸。特に家族的類似の考え方だけでも多くの混乱を解決できるポテンシャルがある。2017/01/18
またの名
10
昔(『論考』)のように緻密な凄い哲学じゃなくて深く考えないで済む楽なやり方に逃げてしまった、とラッセルがケチをつけるくらいなので読み易い。その特性をさらに伸長させた新訳の力添えがあってもなお散漫な印象が消えない文体に訳者はニーチェを対比させるけど、常に考え続けながら自由連想風に言葉が展開するラカンの講義とも類似。哲学的言語の厳めしさに捉われて思考の罠に嵌っている人を、言葉の日常の姿を見せることで助ける地味な営みは、享楽や幻想の魔力に溺れた患者に対するときのラカン的精神分析の姿勢からそこまで離れてはいない。2015/09/25
wadaya
9
単語それ自体に意味は無い。あるのはその単語の使われ方である。そして「名前」の意味はその担い手を指すことによって説明される。私が中学生の頃だったか、1+1=2という数式に違和感を感じて1+1=1+1以外には説明できないと友人に話し、変な顔をされたことがある。それ以来、全く正確ではなくても、ほぼほぼ正確ならOKと自分を納得させてきた。それは世の中の仕組みを理解して行くことに似ていた。「哲学探究」はそんな「言語ゲーム」から始まる。最初はつまらない言語遊びのように感じられたが、次第に懐かしい気持ちになってきた。→2021/12/16
吉野ヶ里
8
再読。一度目より明瞭にわかる箇所は増えたと思う。ただこの分、一度目より驚きというか興奮がなかった。読む時期ではないのに無理に読んでしまった感覚がある。子供が母語を習得するときにやっているゲームという例から言語全体に対して敷かれる「言語ゲーム」という考え方。新しいことは何もいっていないのに道筋を示している。哲学の役割。言語の役割はその使用であり、元エレメントに対応する名前の集合ではない。名前としての使用ももちろんあるけれども。言語の使用がまず先にあり、先例を受けて言語使用はルールを拡張する。言語使用の郊外。2019/10/15