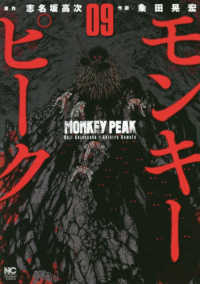出版社内容情報
第一次世界大戦という総力戦から衝撃を受けた日本陸海軍は,戦時に備え平時より軍事力を経済力の可能な範囲で蓄えておく「戦時経済体制」をどのように構想したのか。またアジア太平洋戦争の敗戦に至るまで,この構想はどのように準備・展開され,そして破綻に至ったのかを経済史・経済思想史的視点から詳細に解明する。
内容説明
第一次世界大戦という総力戦から衝撃を受けた日本陸海軍は、戦時に備えて平時より経済力の可能な範囲で軍事力を蓄えておく「戦時経済体制」を、どのように構想したのか、そしてアジア太平洋戦争の敗戦に至るまで、この構想はどのように準備・展開され、そして破綻に至ったのか。経済史・経済思想史的視点から詳細に解明する。
目次
問題意識と視角―戦時経済体制と合理性
第1部 戦時経済体制の構想―総力戦経済体制をめぐって(戦間期の戦時経済思想―日本陸軍を中心に;生産力拡充問題と物資動員計画)
第2部 戦時経済体制の展開―アウタルキーの呪縛(日満支経済ブロックの構想と展開;「大東亜物流圏」の再編と崩壊;日本海軍とアウタルキー思想)
第3部 「戦時期経済」体制に見る軍事工業―航空機と艦船(戦時航空機工業の構想と展開―陸軍航空を中心に;戦時造船工業の造成―潜水艦と戦時標準船)
転換期の経済的背景
著者等紹介
荒川憲一[アラカワケンイチ]
1947年宮城県石巻市生まれ。72年一橋大学社会学部卒業、同年陸上自衛隊入隊(2等陸士)。96年防衛研究所戦史部所員(その後主任研究官)、97年東洋英和女学院大学大学院社会科学研究科修士課程修了、2001年一橋大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学、03年防衛大学校助教授、09年同教授。経済学博士(一橋大学)。元1等陸佐。専門は、戦争と経済(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hurosinki
ワッキー提督