出版社内容情報
ワイマル共和国の自壊とナチズムの台頭,その破局に続く冷戦下の東西両国家の並立から再統一へ――近現代ドイツの歴史は,ナチス・東ドイツという二つの独裁制と市民社会との間の対抗の歴史でもあった。「ヨーロッパ近代」を規定する原理として見直しがすすむ市民社会理念の本質を,ドイツを代表する歴史家コッカが明晰に論じる。
内容説明
ワイマル共和国の自壊とナチズムの台頭、その破局に続く冷戦下の東西両国家の並立から再統一へ―近現代ドイツの歴史は、ナチ・ドイツ、東ドイツという二つの独裁制と市民社会との対抗の歴史でもあった。「ヨーロッパ近代」を規定する原理として見直しがすすむ市民社会理念の本質を、現代ドイツ歴史学界の第一人者であるコッカが明晰に論じる。
目次
1 序章
2 市民文化と市民社会―ヨーロッパの文脈におけるドイツ(意味の両義性がもつチャンス;B¨urgertum―対抗者と文化によって定義された市民層 ほか)
3 独裁制の比較―ドイツ民主共和国の社会史をめざして(なぜドイツ民主共和国の歴史なのか;新たな社会の政治的建設 ほか)
4 困難な過去との取り組み―一九四五年および一九九〇年以後のドイツにおける集合的記憶と政治(西と東のドイツ人はナチの過去とどのように取り組んだのか―一九四五‐一九九〇年;統一後におけるドイツ民主共和国の回想―さまざまな位相、論争的な諸議論 ほか)
5 歴史家、流行、そして真実―最近の五〇年(歴史学―変化しうる学問;第一次世界大戦についての見解の変化―ひとつの例として ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yakumomutsuki
1
Ⅱ「市民文化と市民社会」のパートはなかなか興味深く読んだ.ハーバマスの『公共性の構造転換』の話と大きくかぶる部分があるんだけど,市民(citizen/bürger)の概念から始まり,ドイツにおける市民社会史をなぞっていく.Ⅴ「歴史家,流行,そして真実」のパートでは,コッカ自身,歴史学者としての自戒を込めながら歴史学の傾向について記述している.歴史学者の視座はそのコンテクストから生じており,このつながりを断ち切ることはもはや不可能である.ゆえに,異なるパラダイムも生じ,専門化され,論争も発生する.2011/09/29
トキ
0
読書は二回目からが楽しいと思う。新たな知識に触れるということは出会いであって新鮮である。新たに得た知識が自分のものとして成熟する為にはそれなりの時間が必要であり、同じ内容を読み返すことはそれを促進するだけでなく、新たな解釈と発見を得ることが出来る。二回目はまた、心の余裕が生まれる。読み始める位置を選択出来る。現時点で、私は本書に関しては一回と半分の読書と言える。一年前の私には本書の「Ⅱ 市民文化と市民社会」は手も足も出なかった。今(当時の意味)の私が読む本ではないと思っていたし、事実そうだったと思う。2020/06/30
call
0
二週目。序章で全体の要約を示し、第二章でドイツ語の「市民」という言葉が持つ両義性から市民社会について論じている。第三章でDDRの歴史について、第四章で東西ドイツの歴史認識の変遷について述べられている。最後に歴史学に対して流行が持つ役割を論じている。 読み方として「市民社会」という言葉に引きずられた気がする。第三、四章ではドイツ現代史の中で市民社会が果たすことのできた役割のような形で読み進めることができたが、このせいで第五章がこれまでの文脈とは切り離された章に思われてしまった。2019/02/16
call
0
一週目。ドイツ現代史についての本。第一印象としては、第二章で提示された市民社会を軸に論を進めてるのかな、読めばいいのかなという感じだった。市民社会というと僕にとっては非常にふわっとした概念で、この概念について第二章で詳しく書かれていたので分かり易かった。2019/02/16
-
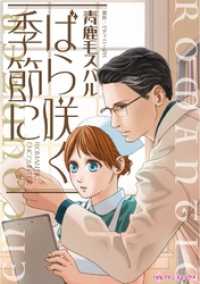
- 電子書籍
- ばら咲く季節に【分冊】 5巻 ハーレク…
-

- DVD
- アルテ DVD-BOX






