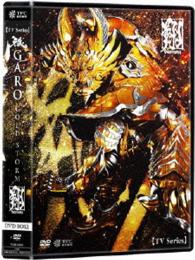出版社内容情報
東日本大震災は,家族やコミュニティの役割と意味について多くの問いを投げかけた.それは,震災によって失われたものとは何か,そして震災前から既に失われていたものとは何かをあぶりだしたのだ.戦後日本にとっての「東北」を歴史的にたどり直しながら,日本の家族のいま,そのありのままの姿を綿密な取材から描くルポルタージュ.
内容説明
東日本大震災は、家族やコミュニティーの役割と意味について多くの問いを呼び起こした。それは、震災によって失われたもの、震災前から既に失われていたものをあぶり出し、戦後日本にとって家族とは何だったのか、「東北」とは何だったのか、という自問自答を私たちにもたらした。本書は、これまで「ロストジェネレーション」や「孤族の国」など時代の転換を証言する新聞報道に携わってきたジャーナリストが、被災地と都市圏、そして現在と戦後を往復する取材から、日本の家族のありのままの姿と、これからの可能性を描く試みである。
目次
第1章 家族と分断(被災の分断 被害の不連続;想定外という言葉;リスク社会と家族;植民地としての東北と家族)
第2章 被災地の力(東北人は忍耐強いか;災害ユートピア;死者との絆;震災と孤独死;不明高齢者と被災地)
第3章 フクシマと家族(原発離散家族;スローライフと放射能;原発で手足ちぎられ;フィリピン人妻と東北;家電と原発;分断を超えて)
第4章 3・11までの家族(集団就職列車;団地の幸せ競争;家族の戦後体制;岸辺のアルバム;団地という密室;孤育ての闇;カーボンコピーの私たち)
第5章 多様化が家族を救う―3・11後の家族(家族を襲うグローバル化;家族機能のアウトソーシング;グローバル・ジャングルでの生存戦略;震災という契機;人生の最後をともに;場所づくり;家族を超えて)
著者等紹介
真鍋弘樹[マナベヒロキ]
朝日新聞記者。1990年、朝日新聞社入社。岐阜支局、東京本社社会部、那覇支局、ニューヨーク支局等で報道に携わる。論説委員、社会部次長を経て、2012年4月からニューヨーク支局長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- DVD
- カラマーゾフの兄弟 2