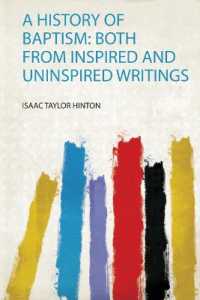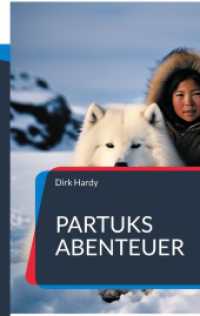出版社内容情報
日本全国のコケの山・森と,山を代表するコケを厳選して紹介.山ファン・苔ファン必携の書!
内容説明
山はコケでにぎやかだ。鬱蒼とした照葉樹林から雲の上の高山まで、多彩な美しいコケたちが、悲喜こもごものドラマを繰り広げている。日本全国のコケの山・森と、山を代表するコケを厳選して紹介。コケから見えてきた、知られざる山の姿も…。足元のコケを通して山、そして地球環境にまで思いを馳せる、山ファン・苔ファン必携の書。
目次
第1部 実践篇(厳選!全国コケの山・コケの森;必見!山のコケ図鑑)
第2部 解説篇(人生いろいろ苔もいろいろ―標高帯別・山のコケの生き方;山のコケ、環境を語る;コケと一緒に山歩き)
著者等紹介
大石善隆[オオイシヨシタカ]
静岡県浜松市出身。京都大学農学研究科博士課程修了。博士(農学)。福井県立大学学術教養センター准教授。専門はコケの生物学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ショア
26
奥多摩の御岳山は全国でも有名な苔スポットだったのか。奥多摩の川苔山は知らなかったが名前からして苔三昧な雰囲気。北と南の間である奥多摩は様々な種類の苔に出会えるとのこと。八ヶ岳高山帯の苔には発がん性のある有機化合物が高濃度含まれていることがわかった。これは日本海側の都市の苔にも類似成分。中国大都市の大気汚染の影響と考えられる。 コロナ禍に訪れた支笏湖の苔の洞門に立ち寄れなかったのが悔やまれる。2022/07/10
水ポテンシャル
18
登山を通して出会える苔について、解説された本。苔登山を夢みて、アイテムを準備し、知識もと思ったが、先に実際見て写真撮ってこの本の順番の方が自分は頭入ってきたかも笑。苔の形の意味、植生との関わり、季節ごとの苔の見方を柔らかく浅めに書かれていたので、初見者にはとても読みやすかったです。植物を見ながら、なぜどうしてこんな形?ここに?を楽しめる人にはおすすめ。あとカラーの写真がめちゃくちゃ綺麗で見に行きたくなります。2020/08/09
S.Mori
15
前半の苔の美しい写真にうっとりし、後半の苔の生態の説明に新鮮な感動を覚えました。濃い緑の苔が山を覆う風景は本当に美しいです。自然の中にある美が凝縮した趣があります。そのような風景を見ることができる土地が日本のあちらこちらにあるのが分かり、嬉しかったです。後半の生態を描いた部分では、苔たちが自分の子孫を増やすために様々な戦力を取っていることを知り、自然界で生き抜くことの厳しさを実感しました。たかが苔だと言うこともできますが、その苔の世界の奥深さを教えてくれる本です。2019/10/29
attsun
9
山に登っていたら苔にも注目するわけで、こちらの本を借りてみた。とてもわかりやすくて面白く、量もちょうどよい。この先生の授業があれば喜んで聞きにいきたいくらい面白かった。そして登って苔を見てみると、いろんな種類の苔があってしかも砲子体があって感動!今までは一括りとしてしか見ていなかったので、世界がまた広がった。入門としてオススメ!2020/06/25
やま
9
大石さんの苔シリーズ。今度は山編です。低山から高山までいろいろな山の苔が紹介されています。読んでいると、山々の苔むした様子が思い出され、森林浴をしている気分です。解説篇では山々の環境に適応して生きる苔たちの様子がよくわかります。高山地帯での適応には感心しました。他の本でも書いてありましたが、ほんの少しでも苔を持ち去ると、その小さな空間が苔の群落を絶滅に追いやるとは恐ろしくなります。ましてや苔で金儲けやそれをマスコミが取り上げるなど、モラルや日本の自然が心配になりました。2019/08/10