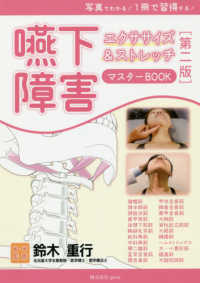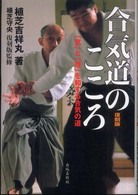出版社内容情報
百万人が涙した『愛と死をみつめて』、松本清張の栄光と挫折、貸本界の帝王・山手樹一郎、読書サークル、映画と名作文学、全集ブーム、生き方本としての『宮本武蔵』『徳川家康』。読書ランキングから時代精神を読む。高度成長期ブックガイド。
内容説明
専門家による文学史は、必ずしも「あの時代の文学状況」の全体を映し出すものではない。では、この国の多くの読者が当時、本当に愉しみ、憧れ、また励まされた本とはどんな書目だったのか。毎日新聞社刊『読書世論調査』、『出版年鑑』の「全国ベスト・セラーズ」などの読書アンケートをはじめ、関連資料を博捜、精読し、「あの時代の文学状況」の全体像をあざやかに描き出す。
目次
プロローグ 文学史とベストセラーのうそ
1 松本清張の栄光と挫折―『点と線』『砂の器』『昭和史発掘』
2 百万人が涙した『愛と死をみつめて』
3 観てから読むか/読んでから観るか―『野菊の墓』『赤と黒』『レベッカ』
4 校外学習としての映画教室と少年少女たち―『二十四の瞳』『次郎物語』『路傍の石』
5 貸本界の帝王・山手樹一郎―『桃太郎侍』『青空浪人』『夢介千両みやげ』
6 読書サークルで勉強する/遊ぶ―『女の一生』『人形の家』『愛の終りの時』
7 全集ブームにあおられて―『旅愁』『嵐ヶ丘』『風と共に去りぬ』
8 「借りて読む」から「買って読む」へ―『宮本武蔵』『徳川家康』、そして百科事典ブーム
エピローグ 敗戦からの再出発
著者等紹介
藤井淑禎[フジイヒデタダ]
1950年、豊橋市に生まれる。慶応義塾大学文学部卒業。立教大学大学院博士課程修了。日本近現代文学・文化専攻。現在、立教大学文学部教授、立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センター長。90年代初めに同時代(作品発表時)の読者による解釈を重視した“小説の考古学的研究”を提唱、以後、作家や作品を同時代の地層上に置いて考察する方法を実践するいっぽう、80年代に消滅した“作品論”の復権をライフワークとしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きさき
nchiba
はるゆう
-

- 和書
- 癒すこと・癒されること