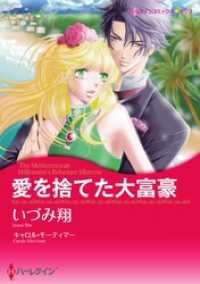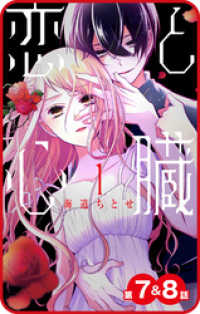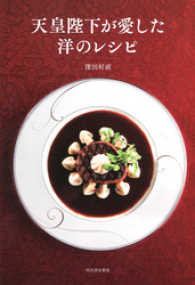内容説明
人生の最後をどこで、どのように迎えるのか…。実際にはどうなっているのか。医師たちによる、新しい試みは、どのように実践されているのか。映画『終りよければすべてよし』をつくった羽田氏が、在宅医療の医師、介護サービス事業の経営者、行政の首長、政策立案者、介護家族などとともに、よりよい「最期」を迎えるために何をしたらいいのか、いま何ができるのか、を語りあう。日本の医療がかかえる課題、そして未来に向けての医療のあり方の可能性を描き出す一冊。
目次
序 なぜ、映画『終りよければすべてよし』をつくったのか
1 在宅医療を始めた理由
2 医者が変わること
3 専門性の高い介護をめざして
4 介護をめぐる制度
5 在宅医療の道に
6 特養ホームのターミナルケア
7 地方からの実践
8 「自宅で死にたい」を実現するために
9 家族を見送って思ったこと
著者等紹介
羽田澄子[ハネダスミコ]
記録映画作家。1926年旧満州大連市生まれ。自由学園女子部高等科卒業。岩波映画製作所に入社し、岩波写真文庫の編集を経て、記録映画の演出に携わり、話題作を次々に発表。現在はフリー。代表作に「薄墨の桜」、「早池峰の賦」(芸術選奨文部大臣賞、エイボン芸術賞受賞)、「AKIKO―あるダンサーの肖像」(文化庁芸術作品賞受賞)、「痴呆性老人の世界」(毎日映画賞他受賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
めい
1
死に方を考えることは、生き方を考えること。自分らしく、人間らしく生きて死たい。そのための社会システムをつくらなくてはならないのだと、思った。2014/06/09
かめかめ
0
高齢社会に伴い亡くなる人は急増していきます。ところが病院は増えません。それどころか病院崩壊で病院機能はますます低下してくることでしょう。ということは福祉施設や自宅での看取りが増えることを意味します。つまり、在宅医療が普及しないととんでもないことになるのです。政府の動きを待つよりも自分たちで行動せよ!ということでしょうか。2011/06/01
もりけん
0
「こんな風に死にたい」とある高齢女性に渡された本。