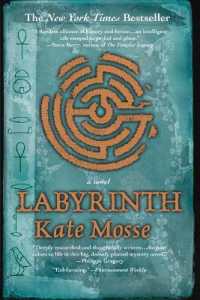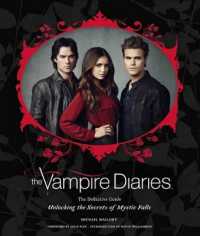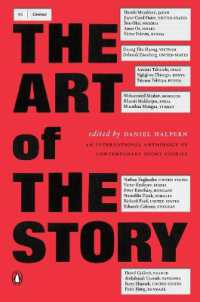内容説明
安倍首相が意欲を示す「憲法改正」。その憲法観・歴史観にはどのような特徴があるのか。明治以来の憲法論議や戦前の立憲政治の経験、戦後憲法史をふり返りながら、日本社会がこれまで憲法をめぐる問題にどのように向き合ってきたのかを考える。その上で、自民党「改正草案」の持つ意味を読み解く。現在の改憲論はこの社会をどのような方向へ連れてゆこうとしているのか。
目次
1 “憲政”としての戦前と“憲法”としての戦後(戦前―“立憲主義”は指導層の共通認識だった;戦後―“個人”の解放が憲法理念となる)
2 戦後憲法史をどう見定めるか(「憲法形骸化」論が見落してきたもの;改憲論の現在―その中での二〇一二年自民党「改正草案」)
3 日本の憲法体験が持つ意味(いま改憲を「決めさせない」こと―「決める政治」に流されないで;世界から受けとったものと世界に向けて返すもの―“普遍”を求めることと“伝統”への愛着と)
著者等紹介
樋口陽一[ヒグチヨウイチ]
1934年仙台生まれ。憲法専攻。1957年東北大学法学部卒業。東北大学法学部、パリ第2大学、東京大学法学部、上智大学法学部、早稲田大学法学部などで教授・客員教授を歴任。日本学士院会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
25
大きめの活字で読みよい。日本の外から保守でなく急進と見られている人たちにより唱えられている改憲は、見通しの効かない将来に連れていく。見極めは次世代に対する責任(9頁)。先ほどドイツの脱原発の本にもあったように、sustainable developmentが問われる。東洋のルソー中江兆民は、人間個人の精神の自立がなくては、と説いた(29頁)。憲法問題研究会は1958年発足。大内兵衛、茅誠司、恒藤恭、矢内原忠雄、湯川秀樹、我妻栄の経済、法、物理を専門とする発起人がいた(46頁~)。 2014/10/02
かんがく
12
自民党憲法改正案が出されて政権交代が起きた際に書かれた本。個人や自由といった普遍的な価値観を、国や家や伝統などによって覆そうとする思惑に対する危機感が述べられている。2022/08/19
coolflat
12
「決める政治」の追求が立憲主義の否定に発展するというのは膝を打つ。マスメディアをはじめ多くは「決められぬ政治」の元凶として衆参の「れじれ」を槍玉に挙げるが「決める政治」というのはとんでもないという事だ。近代デモクラシーは単純多数決では変えられぬ約束事としての基本法によって権力を制限する立憲主義の形をとっている。大日本帝国憲法下においてさえも立憲主義は建前として共有されていた。「決める政治」を求めてゆけば立憲主義をとる憲法が邪魔になる。現在の日本はある意味大日本帝国以下だ。決めさせない政治、ねじれ、万々歳。2015/04/03
ひかりパパ
7
改憲論者が現憲法はアメリカからの押し付けられた憲法だからけしからんと批判する。当時の自由主義的な憲法学者でさえ、天皇主権を前提にした憲法草案しか作れなかった。国民主権など頭になかったのだ。そもそも自分で作れなかったのだ。加藤周一は自分で作れなかったのはなぜなのかということこそ重大問題だと言う。明治憲法の成り立ちも不平等条約の解消のため独立国家の地位を回復するためやらざるを得なかったことを考えると外圧によるものである。押し付けうんうんの議論はあまり意味がない。侵略戦争の否定が戦後の国際秩序の出発点(続く)2015/01/04
Hisashi Tokunaga
7
樋口先生が危惧するほど、このたびの自民党の改正草案は出来が良くない。安倍さん他この草案作成に関わった自民党のメンバーが憲法論議に熟知していない、あるいは憲法論にほぼ無知だからでしょう。過去の憲法調査会など通過してきた自民党の改正案はこんなに粗雑ではなかった。05年のときなんかは、中曽根の前文案はバッサリ削除された。この案で憲法改正発議はほぼ不可能。自民党の真摯な取組振りが疑われ、政権維持が危うい。今回の自民党草案のような貧弱な憲法論を敵にするようでは、碌な憲法論争の深化はありません。もうやめましょう。2013/08/13