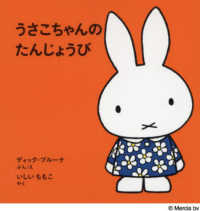出版社内容情報
前講座の刊行から20年.この間,日本のあり方も世界におけるその位置も大きく変動した.いま日本はどこにいるのか,またこれからどうあるべきなのか,今こそ歴史に問い直すときである.アジアさらには世界との新たな関係を意識しながら,原始・古代から現代まで,政治体制を中心に,それを支えた経済・社会構造,宗教・文化等の大きな流れを描き出す.学界の第一線研究者の総力を結集.
遣使や留学生,僧によって伝えられた制度に倣いながら,律・令が編纂され,法にもとづいた支配体制をもつ中央主権国家が成立した7~8世紀.平城京が築かれ,大仏が造立された奈良時代,大陸・半島の影響を多く残しながら,やがて日本独自の国家,文化が育まれ,形づくられていく過程をたどる.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takeshi3017
4
岩波書店の歴史本第3巻。遣唐使の派遣から律令制の形成、(近江令、浄御原令、大宝律令、養老律令)遷都、東大寺の大仏開眼、聖武天皇の受戒など。この巻では特に仏教にまつわる様々な話が出てくる。奈良時代といえば鎮護国家思想として仏教がもてはやされたが道鏡の出現あたりからだんだん怪しくなってくるような。もちろん真言宗の空海、天台宗の最澄なども出てくるが。詳細→ http://takeshi3017.chu.jp/file8/naiyou30303.html2021/02/23
Takashi
0
ようやく読破。奈良時代の政治・宗教・文化が通史的に広く論じられる。唐の立ち位置と周辺諸国の位置づけを鋭く論じた「天平文化論」、神祇と仏教の相克を丁寧に論じた「律令国家と神祇・仏教」、そして口頭決済という伝統を引き継ぎつつも、次第に文書に比重をおいた決済システムへと変貌し、それが官衙施設の充実とも連動すると説いた「律令官僚制と天皇」などがとくに印象に残った。2015/07/20
際皮
0
だいぶ難しかったが、「遣唐使の役割と変質」と「律令国家と神祇・仏教」は面白い。ただ、道鏡への皇位継承が失敗した理由を、革命思想を律令国家が受け入れなかったから、と簡単に書いてあるが、もう少し詳しい説明が欲しいとも思った。2021/07/29
-
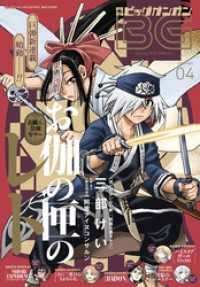
- 電子書籍
- 月刊ビッグガンガン 2023 Vol.…
-

- 電子書籍
- 皇太子の婚約者として生き残る【タテヨミ…