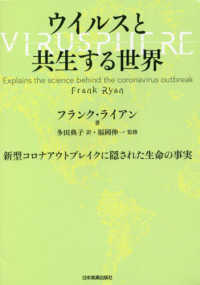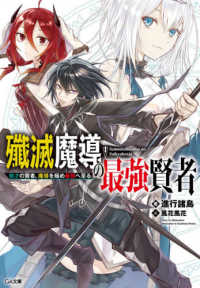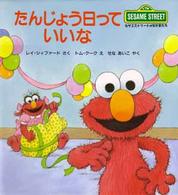出版社内容情報
今日,情報化・国際化・高齢化といった社会の基本構造の変化のなかで,日本社会は過去には予想だにしえなかった問題を抱え,法的にも,これまでの枠組では十分に検討されえない多くの現象を発生させています.このような現実に対して何をなしうるのか,わが国の法学の現状を徹底的に見直しつつ,考察します.
目次
1 国家の動揺と法の変容(国民国家の基本概念;承認と自己拘束―流動する国家像・市民像と憲法学;人権理論の変容;積極的平和論の基礎―個人対国家の法を超えて)
2 市民社会と法(国家権力の正当性とその限界;国家と宗教;国家と文化)
3 改革を迫られる国家と法(行政改革と官僚制;転換期の税制改革;新たな地方分権・自治の法)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
フクロウ
3
石川健治「承認と自己拘束」。日本の憲法学の基礎を作り上げたといって過言でない美濃部達吉のタネ本、ゲオルク・イェリネックの『一般国家学』。その身分論の含意はしかし、宮沢俊義の権利論に歪めて誤読誤訳され、著名な自由権、社会権、参政権といった今日まで受け継がれる類型論となった。しかし、イェリネックの本来の筆致は、絶対王政から市民革命までを主権を有する国家が国内的な正統性を唯一付与できる、つまり承認できる団体として成形される過程として描き、自由を単一の、主権国家からの無関心の領域として確保することにあった。2023/09/09
真のなすだすん
0
承認と自己拘束2012/10/22