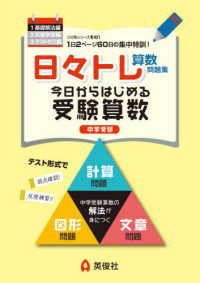内容説明
「大東亜」戦争期を通じて、日本のアジア進出と異民族統治はさらに拡大していった。その支配は各地に何をもたしたのか?第七巻では、イデオロギー、統治のテクノロジー、経済等の諸側面から「大東亜共栄圏」の実相に迫るとともに、今なお各地の脱植民地化の過程に根深い影響を与える、支配の再編・継続の問題を考察する。
目次
1 統治のテクノロジー(植民地統治と南方軍政―帝国・日本の解体と東南アジア;満州国における民族と民族学;イスラーム政策と占領地支配;戦時期朝鮮の治安維持体制)
2 資源の戦争(帝国内の物流―米と鉄道;日中全面戦争後の在日本華僑・印僑ネットワーク;「南進論」と「北進論」)
3 抵抗と協力の間(戦時期朝鮮における朝鮮人地方行政職員の「対日協力」;汪兆銘政権論;内モンゴルにおける「蒙疆」政権;東南アジアにおける「対日協力者」―「独立ビルマ」バモオ政府の事例を中心に)
4 支配の継続と再編(帝国の忘却―脱植民地化・紛争・戦後世界における植民地主義の遺産;基地論―日本本土・沖縄・韓国・フィリピン;日本の再軍備―警察予備隊の創設を中心に;倍賞と経済進出)
著者等紹介
倉沢愛子[クラサワアイコ]
1946年生。慶應義塾大学教授
モーリス‐スズキ,テッサ[モーリススズキ,テッサ][Morris‐Suzuki,Tessa]
1951年生。オーストラリア国立大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
小鈴
8
倉沢愛子「帝国内の物流ーー米と鉄道」のみ読了。東南アジアは米の宝庫。太平洋開戦前、統計上では大東亜共栄圏内の不足地域で約200万トンが不足し、一方で余剰地域は、548万トンで差し引き350万トンの余剰が出るはずだった。しかし結果として食糧不足が生じた。天候不良などではなく流通政策の不備、輸送力の低下からよみとく。政策の失敗による飢饉は人災だ。今の立場から見ると意外だが戦前日本の米自給率は100%ではなく植民地に依存していた。2016/11/08
ワッキー提督
3
論文集として本書のタイトルに関係する様々な論文が収録されているが、特に大日本帝国の戦争遂行と資源の関係性に踏み込んだ、倉沢・森山両先生の論文が最も印象深く、開戦前から総力戦遂行が既に破綻していたことと、その状況下で東南アジアを占領し「帝国」に組み込んだことが何をもたらしたのか、非常に明瞭に示されていた。それ以外には日本以外の領域の開戦前や戦時の住民の動向、特に朝鮮のそれに関する研究が興味深かった。2022/01/30