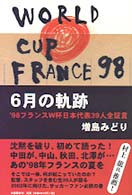出版社内容情報
新旧・東西の諸帝国と比較しながら「大日本帝国」の植民地化の実態をおさえ,帝国拡大のプロセスと支配システムの位相をたどり,最新の帝国主義理論を援用して帝国秩序と植民地経営の特質を考察する.
内容説明
アジアを侵す「大日本帝国」。問い返す日本的「近代」の総体と遺産、いま開かれる歴史の扉。
目次
1 近代世界の形成と植民地(東アジア新旧帝国の交替;東アジアの経済圏―戦前と戦後;中華帝国の「近代」的再編と日本)
2 近代日本の膨張と植民地(内国植民地としての北海道;日本の近代化と沖縄;千島列島の領有と経営;関東軍の内蒙工作と蒙疆政権の成立;帝国日本の東アジア支配;日本植民地支配下のミクロネシア)
3 帝国主義論の現在(帝国主義の政治理論;帝国主義論と戦後世界;英国と日本の植民地統治)
著者等紹介
大江志乃夫[オオエシノブ]
名古屋大学経済学部卒、文学博士。茨城大学名誉教授。日本近代史・軍事史
小林英夫[コバヤシヒデオ]
東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取得中退。文学博士。早稲田大学アジア太平洋研究センター教授。アジア経済論
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Sapporo Shiojiri
2
八章江口圭一「帝国日本の東アジア支配」/日本の植民地支配を、①日清から日露戦争、②韓国併合から第一位世界大戦、③ワシントン体制への順応と挑戦の3期に分ける。/日本植民地帝国史は、集約性全方位的な膨張ーと表現できる、という。1941年の独ソ戦開始に接した御前会議での「情勢の推移に伴ふ帝国国策要綱」が「「支那事変処理」を継続しつつ、南部仏印進駐と関東軍特別演習を企てた」ことを「放射型構造のもたらした貪欲と混迷の表現」【186頁】と評価。概説としての価値は未だ損なわれていないが、表現は時代を感じるなあ。2019/11/08
-
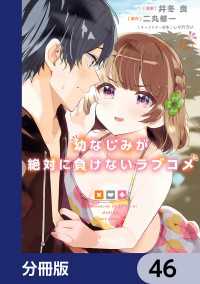
- 電子書籍
- 幼なじみが絶対に負けないラブコメ【分冊…
-
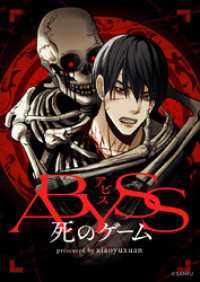
- 電子書籍
- ABYSSー死のゲームー【タテヨミ】第…