内容説明
「過激」、「極めて不適切な教材」として、障害のある子どもたちの性教育に加えられた政治家の攻撃。学校を守らなかった東京都教育委員会。メディアによるバッシング。全国的にも注目された裁判(東京地裁2005年5月提訴~2009年3月判決)で、何が裁かれたのか。「教育の自由」をめぐる必読書。
目次
1 七生養護学校で何が起こったのか
2 裁判で語られたこと
3 判決の意義
4 生養護学校の事件が問うたもの
著者等紹介
児玉勇二[コダマユウジ]
1943年東京生まれ。1968年中央大学法学部卒。71年裁判官就任。73年弁護士となる。東京弁護士会「子どもの人権と少年法に関する委員会」、日本弁護士連合会「障害のある人に対する差別を禁止する法律に関する調査研究委員会」などの委員として活躍。チャイルドライン支援センター理事、立教大学非常勤講師。七生養護学校の事件では、原告側の弁護団団長をつとめる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あや
35
障害があろうがなかろうが、体は発達するし異性にも興味を持つ。人を好きになるし、結婚だって考える。性に対する知識というのは必要不可欠なのに、人はそれを遠ざけてしまいがち。そんな中で七生養護学校は保護者や専門家との連携を充分に行い、子どもたちのための性教育を行ってきたのに。子宮体験袋にせよ箱ペニスせよ、教育に対する知識が不十分な人間によって糾弾されることあってはいけないことなのにな。性犯罪の被害者にも加害者にもならないために、そして彼らの人生がより良いものになるためには必要不可欠な教育だと私も思いました。2014/11/21
あらま
1
真っ当な内容。本当は七生養護学校の教育の中身をもっと知りたいんだけど、弁護士の本だからしかたないな。2010/02/27
りんふぁ
0
障害があるからこそ、性教育は必要。始めはわからなくても、繰り返すことによって、ちゃんと理解出来るんですから。わざわざ卑猥に見えるように撮る教材写真。悪意前提にしか思えません。2015/03/05
はばねろ
0
ゼミ課題で読んだ"2011/10/19
-
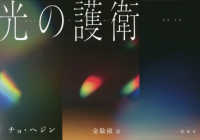
- 和書
- 光の護衛




