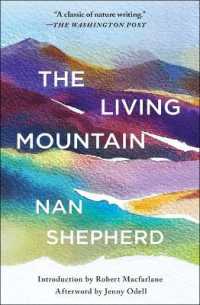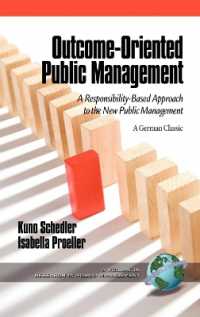内容説明
底が抜けてしまったかのような不安定さが続く日本社会。生きる基盤すら奪われてしまう状況がある一方で、現実を変革しようという新たな運動が胎動しつつある。ポスト新自由主義の時代に向けて、格差と貧困の現場で格闘する2人と、第一線の研究者3人による骨太の議論が、社会保障、運動、そして政治の本質を伝える。
目次
第1部 反・貧困と市民社会(貧困問題を生み出す構造と、果たすべき責任(湯浅誠)
パネルディスカッション(湯浅誠、中島岳志、宮本太郎、山口二郎))
第2部 プレカリアートの乱?二一世紀日本の若者と貧困(トークセッション 貧困がもたらす社会の崩壊(雨宮処凛vs.中島岳志)
パネルディスカッション(雨宮処凛、中島岳志、宮本太郎、山口二郎))
著者等紹介
雨宮処凛[アマミヤカリン]
作家・プレカリアート活動家。1975年生まれ
中島岳志[ナカジマタケシ]
北海道大学公共政策大学院准教授。1975年生まれ。南アジア地域研究
宮本太郎[ミヤモトタロウ]
北海道大学大学院法学研究科教授。1958年生まれ。比較政治・福祉政策論
山口二郎[ヤマグチジロウ]
北海道大学大学院公共政策大学院教授。1958年生まれ。行政学・政治学
湯浅誠[ユアサマコト]
NPO法人自立生活サポートセンター・もやい事務局長、反貧困ネットワーク事務局長ほか。1969年生まれ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kotte
7
「はじめに」で宮本太郎先生が書いているように2008年12月に開催された北海道大学大学院法学研究科主催シンポジウムの記録です。2008年末はリーマンショック後の経済混乱による派遣切りなどが話題になった時期であり、貧困問題が可視化された時期といえます。本書が書かれた頃と比べれば、失業率など表面的な雇用情勢は改善されていますが、低賃金で不安定な労働を余儀なくされる非正規労働者の現状は変わりありません。非正規労働者の待遇改善が叫ばれるものの、変わらないまま本書の出版から今まで時間が過ぎてしまったといえます。2017/01/04
すのう@中四国読メの会コミュ参加中
3
赤ん坊に対してコミュニケーションを一切取らず、最低限の世話だけして育てた場合、死亡すると聞いた。人にとってはコミュニケーションがとても大切。人との繋がりがあるからこそ生きていける、そんなこともあるはず。けれど、それが消滅しこつつある現在。これは人災だ。2013/04/18
あゆさわ
2
ざっくりとした経済にかかわる最近の政治史という感じ2016/06/10
D21 レム
2
少しでも変った人がいたら「危ない人」とみなされ通報されてしまう社会。雨宮処凛のプレカリアート(不安定な労働者)運動。人との繋がりや金銭や心の「溜め」が失われているため、すぐにホームレスになってしまうしくみ。秋葉原事件は「心の闇」なんかではなくて、社会や労働問題。これを促進することになった小泉改革。向かうべきは社会のしくみを変えること。しかし、非常に困難。2009年の本。2012/05/11
ふぇるけん
2
日本の貧困問題について、すごくよくまとまっています。2010/03/08
-
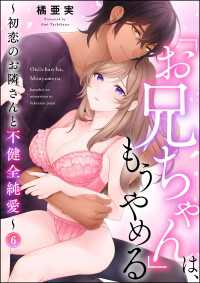
- 電子書籍
- 「お兄ちゃん」は、もうやめる ~初恋の…