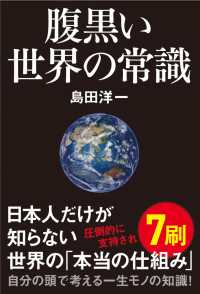出版社内容情報
いわゆる「学力低下」問題の議論が沸騰し,「少子化による受験競争の緩和」「ゆとり重視の教育改革の結果」等が原因として挙げられているが,真の処方箋はあるのか.具体的なデータにもとづき,錯綜した議論を解きほぐす.
目次
1 創られた危機と無視される実態
2 危機の実態―「学び」からの逃走
3 「学力低下」の真相
4 「勉強」の時代の終わり=東アジア型教育の終焉
5 社会の変貌と教育改革の失敗
6 「勉強」から「学び」へ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
スプーン
33
「ゆとり教育批判」を含む教育改革を訴えた一冊。「座学」から「出会いと対話の学び」へ変革せよと言っています。ここで挙げられている日本の問題点が、21年後の現在でも一切解決していない所が、非常に不気味。2021/10/10
rigmarole
5
印象度B+。内田樹が『下流社会』で言及していた限りでは、子どもの心理状況を分析したものではないかという先入観を持っていましたが、統計データを多用し、因果関係を推論しているところでは世界の変化についての著者の見方を述べた、存外社会学的な本でした。要旨は、産業・社会構造の変化に旧来の教育政策・教育システムが対応できず破綻に陥り、それが子どもの勉強しなくなった原因であるということ。著者の歴史解釈をそのまま鵜呑みにしたくはないですが、教育の問題である「『学び』からの逃走」をうまく社会の変化によって説明しています。2017/09/20
Riopapa
3
この20年間で状況は変わった部分もあるが、新自由主義と新保守主義の狭間で日本の教育が揺れ動いているのは同じである。小中学校には様々な変化が見られるが、高校はまだまだという気がする。2022/01/31
Takao
2
2000年12月20日、第1刷。たぶん出版直後に読んでいるので、ほぼ14年ぶりくらいの再読。もしかしたら再再読。現場では最近やたらと「グループ学習」が強調されるが、「かたち」だけが追われているような気がしてならない。旧態依然たる私自身は批判できる立場にはないが、佐藤学さんが最後にあげた、「モノや人やこと」との出会いによる「活動的な学び」、他者との対話による「協同的な学び」、知識や技能を獲得し蓄積する「勉強」から脱し、知識や技能を表現し共有し吟味する「学び」、の3つの課題に取り組んでいきたい。2014/11/03
S
1
日本の子どもの校外学習時間の圧倒的な少なさはとても身につまされるし、学びと勉強の差異について今一度自分でも考え定義し直さなければならないなと思った。データについては出版年相応に古いので最新のものを要確認。習熟度別への警鐘はなるほどと思った。2020/02/23