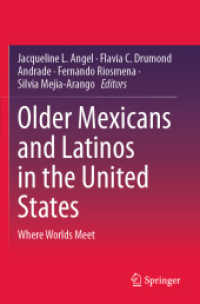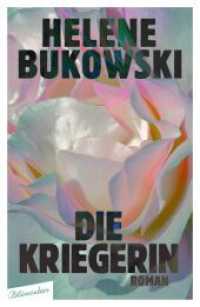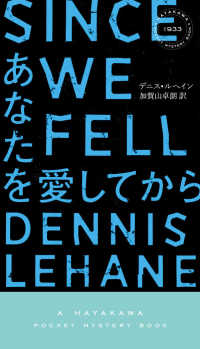出版社内容情報
文化とは何か,それが人間社会に果たす役割は何か.宗教・芸術からイデオロギー,政治に至るまで,さまざまな文化現象の背後に一貫する意味の体系を探り,文化が象徴として機能するシステムを解明する.
内容説明
文化とは何か、それが人間社会に果たす役割は何か、世界的に高名なギアーツが、多彩な文化現象の背後に一貫する意味の体系を探り、文化が象徴として機能するシステムを考察する。2では、イデオロギーやナショナリズムをめぐる政治の文化的な考察、劇場国家論、レヴィ=ストロースの評価、バリの闘鶏に関する有名な分析などが展開される。
目次
第4部(文化体系としてのイデオロギー;革命のあと―新興国におけるナショナリズムのたどる道;統合的革命―新興国における本源的感情と市民政治;意味の政治;過去の政治、現在の政治―新興国理解のための人類学の応用に関する若干の覚え書き)
第5部(頭脳の野生―レヴィ・ストロースの業績について;パリにおける人間・時間・行為―文化の分析に関する考察;ディープ・プレイ―パリの闘鶏に関する覚え書き)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
7
「厚い記述」をスライスした薄いパンを重ねたものに喩えたG・ライルの区別を人類学領域に導入した著者は、複数のサブシステムの中で1つが浮かび上がって「図」となり、他は「地」となる動的システム全体の「薄い記述」を、イデオロギーと名付けた。本書最終章にあるバリ島の闘鶏に関する記述では、儀礼はバリ島人が解釈した彼ら自身の現実のモデルであり、人類学者はその解釈を通してバリ島の文化システムを解釈する。人類学者の「厚い記述」はそのような「薄い記述」(図)の背景に埋没するサブシステムとの象徴的機能を注視することから始まる。2024/04/09
いとう・しんご
1
「人間は自分自身がはりめぐらした意味の網にかかている動物である」1巻P6というP.リクール「イデオロギーとユートピア」にあった引用に惹かれて読みました。両著はいわば相聞歌で、解釈学的基礎研究と社会学的応用研究となっている。ポスト・コロニアル研究として読んでも面白い。2020/10/17
たけぞう
0
やはり「ディープ・プレイ」を扱った最後の章が面白かった。2012/03/03
Kanou Hikaru
0
本棚整理中・・・ 友人知人に紹介したい本として登録