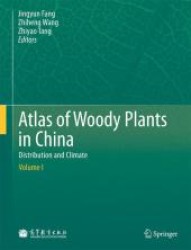出版社内容情報
東欧の戦後秩序を決定したと言われているヤルタ会談.しかし,東欧諸国には独自の戦後構想と未来への期待があった.やがて東欧が完全に「東側」に組みこまれていき,冷戦は人々の願いを潰していった.
内容説明
ヤルタ会談は、東欧の戦後秩序を決定したと言われている。しかし、大国の取引きとは別に、東欧諸国には独自の戦後構想と未来への期待が存在していた。やがて東欧が完全に「東側」に組みこまれていくまでに、冷戦は人々のどんな願いをつぶしていったのだろうか?
目次
はじめに シチェチンとトリエステ
冷たい戦争の「起源」―大連合の矛盾とヤルタの妥協
民衆の戦後を求めて―東欧内部の戦後構想
人民の民主主義―戦後復興と「新しい道」
岐路に立たされた東欧―鉄のカーテンの内と外
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
119
表紙の三人の顔に浮かんだ笑みが悪寒をもよおさせる。その1年後に『鉄のカーテン』を声高に宣言非難したチャーチル。政治家とはまず自国の利益を考えるものだろうが、 その足で誰を踏みつけていた?大英帝国はまだまだ植民地を支配していたのに、東欧諸国はソ連の下であえいでいると言うのか。確かに彼らはあえいでいた。東欧各国において、抵抗軍と英国に本部を置く亡命政府、共産党と他の党、貧農と富農の対立はバラバラであった。とにかく目指したのものは、自治国家。カーテンは、英国が作り、ソ連が引いたということになるのだろうか。2017/06/06
扉のこちら側
61
2016年1125冊め。冷戦の起源、東欧内部の戦後構想、任民の民主主義。「鉄のカーテン」とは言われるものの、「ソ連・東欧圏」が一枚岩ではなかったことがわかる。鉄のカーテンは一枚ではなく、「二枚の鉄のカーテン」だった。1991年6月13日発行なので、この後どんどん火種が大きくなっていくのだな。2016/12/21
rbyawa
1
ヤルタ会談そのものを、というより、このヤルタ会談を「きっかけ」として戦中から戦後に掛けて起こったことを順番に追って行く構成なのだが、、、えー、これ、正確に誰のせい、と表現するのがどうしても違和感があるというか、少なくとも「ソ連が悪い」で済ませられる側面がこの本までの時代にはただの一つもなかったことが逆に衝撃だった分、自分の浅はかさってものをしみじみと感じる。社会主義は確かに外来のものであり、東欧は確かにソ連の側に(英国の手により)譲られたけれど、東欧の運命は東欧自身が演出したものだと思う。歪みはしたが。2010/02/04