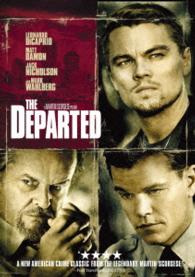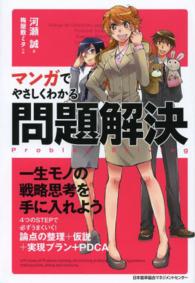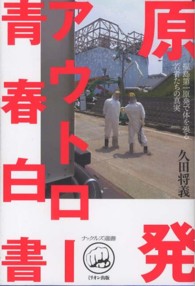出版社内容情報
「道」とは,人類と世界を動かす根源的原動力である.芭蕉においては「道」が俳諧を生み,道元にあっては宗教的境涯と学問が現成し,キリストとその共同体では歴史と神学が創造された.東西思想における「道」を解明.
内容説明
「道」とは、人類と世界の歴史を動かす根源的原動力である。芭蕉においては「道」が俳諧を生み、道元にあっては宗教的境涯と学問が現成し、キリストとその共同体では歴史と神学が創造された。東西思想の出会いの現代的命運から生まれ、このような道の働きを解明する本書は、模索する現代人に知的刺激と精神的力を与える。
目次
序・道をたずねる旅
1 芭蕉の「道の思想」
2 道元の「道の形而上学」(求道と出逢い;道の「活き」に満たさる;道元の「宇宙遊戯」)
3 道の形而上学(神の慈しみ深い「活き」;「道なる御言」の全体知とその展開;「道なる御言」の「活き」の具現的内実;十字架から復活への力働的な「活き」)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
袖崎いたる
7
道とはなんぞや。武道や神道やと「道」のつく言葉があるけど、そういう「道」を言葉としてだけ呑み込むと支障がある、そんな「道」のことを、問うている。その問いの成果は「キリスト=道」へと結集していく。その都度立ち寄る先人は芭蕉と道元、そんでイエス。この本でわかるのは「道」はアタマでやるのではなくカラダで活きることによってこそ歩めるということ。つまり「学」ではない。この点から理性は退場勧告を敷かれる。道の歩みかたに関しては芭蕉から旅感覚をうけとり、道元からはその歩みはつねに道にありという悟達をうけれてよきである。2024/08/19
ナディル
2
【キリスト教の核心巻末リストより 5】カトリック神父として大森曹玄の下で禅を学んだ著者が日本古来の道の思想を芭蕉と道元を例に読み解いた上で、キリスト教を道の思想として捉え直そうとする労作。こんなキリスト教観があってもいいんだと知れて少しホッとしました。神は哲学者の神ではなく、生ける神(パスカル )。聖書はただ読むものではなく、もっとアクチュアルで実存的なもの、共生態としての身(竹内敏晴)を通じての身読を勧めています。2024/01/03
なつき
1
【2016/03/26 はしプロ宗教4】『道の形而上学―芭蕉・道元・イエス』読了。ほんらいはキリスト教でなくキリスト道だとし、日本だからこその道の解釈をおこなっていく。神や神的なものの「活き」を非常に重視する。これは「はたらき」と読む。また、聖書は身読すべきものであると強調する。2016/03/26
-

- 電子書籍
- MS図鑑 U.C.0090年代のネオ・…
-

- 電子書籍
- ダークマリッジ~疑惑の婚約者と消された…