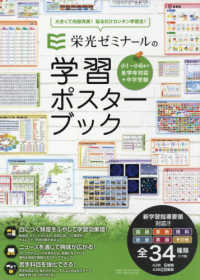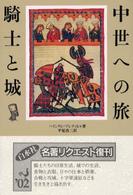出版社内容情報
人間の連帯は,他者が被る残酷さへの感性,想像力を拡張することで達成されるべき目標なのだ.20世紀の代表的哲学者が,ありうべき社会はいかに構想されるかという課題に,リベラル・ユートピアの可能性の提示をもって応える.
内容説明
人間の連帯は、真理の哲学的な探求によっては不可能である。他者が被る残酷さに対する私たちの感性を拡張することによって、連帯は達成されるのだ。20世紀後半を代表する哲学者が、ありうべき社会はいかに構想されるかという課題を、永遠に自由を実現してゆく終わりなき過程である「リベラル・ユートピア」として描き直す。世界中に大きなセンセーションを巻き起こした「哲学と自然の鏡」の政治哲学的帰結―衝撃の問題作。
目次
第1部 偶然性(言語の偶然性;自己の偶然性;リベラルな共同体の偶然性)
第2部 アイロニズムと理論(私的なアイロニーとリベラルな希望;自己創造と自己を超えたものへのつながり―プルースト、ニーチェ、ハイデガー;アイロニストの理論から私的な引喩へ―デリダ)
第3部 残酷さと連帯(カスビームの床屋―残酷さを論じるナボコフ;ヨーロッパ最後の知識人―残酷さを論じるオーウェル;連帯)
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キク
62
「100分de名著」で知った。『文学やルポルタージュを使って他者への共感能力を育て「われわれ」という意識を拡張し続ける』すごい文章だ。成長とは、いや人生とは「どこまで【われわれ】という言葉に多くのものを含めるようになれるのか」ということなのかもしれない。多分、僕の「われわれ」という言葉に含めるものはすごく少ない。というか「われわれ」や「僕たち」という主語をほぼ使わない。いつも「僕」と「他者」という言葉を頭の中で使っている。なんか、いろいろ考えさせられた。2024/03/14
ころこ
43
「偶然性」「アイロニー」「連帯」を各3章ずつ論じていますが、これは、「言語」「個人」「社会」にそれぞれ当たります。最初の「偶然性」が何を論じているのか分からないと感じるかも知れません。その場合は、最後の章のから遡って読むことをお勧めします。リベラルとは残酷さについて考えることですが、世界が残酷なのではない、他人がし得ることが残酷なのだ。しかし本書の議論は、その上で人びとの連帯を可能にするのは、同一化ではないというところにあります。人々が同一の思考をして同一の価値観を持つと考えられたのは近代までであり、現在2021/01/20
逆丸カツハ
34
なかなかいい文章だった。知識人が私的に抱く志として優れているように思った。ただ、自分の哲学的な立場から見てみると、いくらかの前提は共有しているが、いくらかの前提は全く違っていて、方向性の違う異なるゲームをしているなぁと思った。2025/10/25
さきん
25
人々の価値観や言葉は、偶然性に寄って決められており、各々の正義がぶつかって争いはやまない。普遍的な理性、道徳は存在しないという立場。よってお互い争いなるべくなしにやってくためには、他者の価値観を尊重し、自己の価値観を相手に押し付けないし、あくまで自律すること。 そこに連帯、協力の可能性を見いだしている。 全員が相手に配慮示せる保守主義者になれるかということだろうか。アイロニーやリベラルの言葉の定義が語彙そのものとは違うので、読み難い。2025/01/18
CCC
14
私的領域と公的領域どちらも押さえた究極の真理を見つけられるという考え方を破棄し、すべての思想が偶然の産物であることを受け入れるアイロニストになること。そして残酷さを最悪のものと考えるリベラリストになることを薦めている。偶然性に重きを置き、信仰ではなく共感力を求め、根本的問題より個別的問題を重要視する姿勢は、個人的には共感しやすかった。オーウェル、ナボコフの副読本としても面白かった。特にナボコフの『ロリータ』は、自分が不感症な読み方をしていたのがわかったので、いつかは読み直したいと思った。2023/10/19